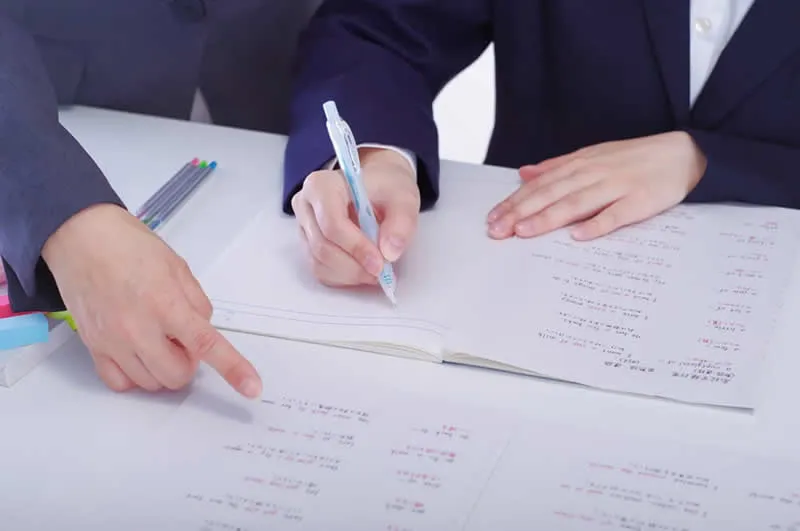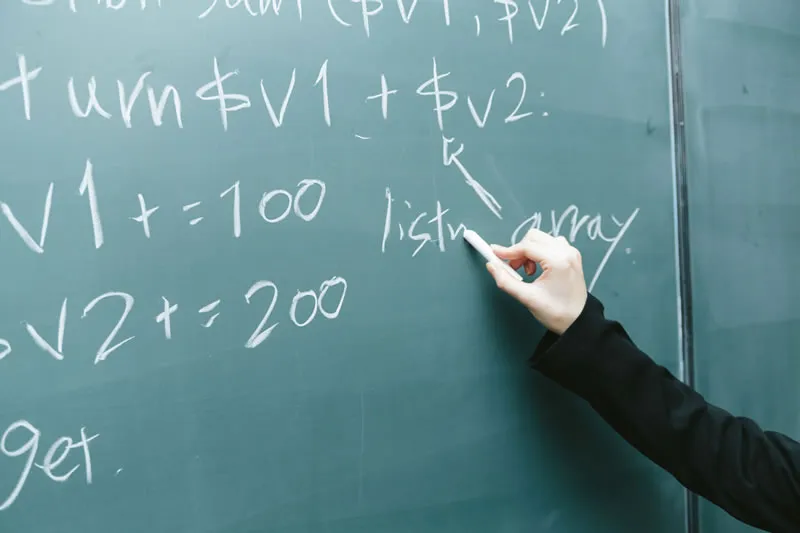- 公開日2025/04/08
- 最終更新日2025/04/08
9歳の壁とは?学習のつまずきの原因と乗り越えるためのサポート方法

目次
小学校中学年頃になると、多くの子どもが学習や生活の中で大きな変化に直面します。これがいわゆる「9歳の壁」と呼ばれるものです。今まで順調に学べていた子でも、急に授業についていけなくなったり、勉強に苦手意識を持ち始めることがあります。こうしたつまずきは、単に勉強量や内容の難易度が上がるだけではなく、思考力や語彙力、友人関係など成長に伴う心身の変化が複雑に影響していることが特徴です。
そこで、本記事では「9歳の壁」とは何か、その原因や起こりやすい学習のつまずき、親ができるサポート方法について解説します。9歳の壁を乗り越え、学ぶことへの自信を育むために、ぜひ参考にしてください。
9歳の壁の特徴とは?

小学校3~4年生頃、約9歳の時期は子どもの成長において重要な転換点となります。これを「9歳の壁」と呼びます。
この時期には脳の発達により、学習内容の変化や自己認識の深まりなど、さまざまな面で大きな変化が訪れます。子どもたちは新たな課題に直面し、乗り越えるべき壁が立ちはだかります。
以下では、9歳の壁の特徴と、子どもたちがどのような変化を体験するのかを見ていきましょう。
9歳の壁とは?どんな変化が起こるのか
9歳の壁とは、小学校中学年(9~10歳)の時期に子どもたちが経験するつまずきや劣等感、自己肯定感の低下などの現象を指します。文部科学省の資料では、この時期を「幼児期を離れ、物事をある程度対象化して認識することができるようになる」転換期として説明しています。
この時期には、子どもの脳の発達により抽象的な概念も理解できるようになり、自分を客観的に認識する力が育ちます。これは成長の証ですが、同時に発達の個人差も顕著になるため、「自分はできない」という劣等感を抱きやすくなります。
学習面では、低学年の目に見える具体的な学習から、イメージが必要な抽象的な内容へと移行します。たとえば、算数では小数や分数など具体的にイメージしづらい内容が増え、理解に苦しむ子どもも少なくありません。また、友人関係も深まり、より複雑な人間関係を築く時期となります。
参考:文部科学省|子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題
9歳の壁が学習に与える影響
9歳の壁の時期には、学習内容の抽象度が高まることで、これまでの学習方法が通用しなくなるケースがしばしば見られます。低学年では単純な計算問題や暗記が中心でしたが、中学年になると文章題や論理的思考を必要とする問題が増加します。
たとえば算数では、足し算や引き算、九九といった比較的単純な計算から、図形や小数、分数、グラフなど概念理解が求められる内容へと変わります。文章問題も難しくなり、思考力が一層問われるようになるため、つまずきのきっかけが増えていきます。
国語においても、説明文などで身近ではないテーマの文章を読み解くことが求められ、「葛藤」など日常ではなじみのない語彙が登場することで、理解しづらさを感じる子どもが増えます。理科でも電気や水の状態変化など、目に見えない現象や抽象的な概念を理解する必要が出てきます。
こうした変化に対応できないと、子どもは自信を失い、「自分は頭が良くない」「他の子よりできない」などと悲観し、学習意欲が低下してしまうことがあります。勉強面でのつまずきが生じた際は、問題だけに取り組むのではなく、根本原因までさかのぼって復習する習慣を身につけることが重要です。
9歳の壁が生まれる原因

9歳の壁が生じる背景には、この時期特有の発達段階による変化があります。子どもたちは小学校3~4年生になると、学習内容の抽象度が高まるとともに、脳の発達により自分自身を客観的に見られるようになります。この時期の子どもは、まだ幼さを残しながらも、少し大人びた言動も見せ始めます。
そんな過渡期に子どもたちが直面する壁の主な原因を見ていきましょう。
思考力が求められる学習へ移行する
小学校低学年の学習は、身近なものや具体的な事象が中心となっていました。しかし9歳頃になると、学習内容が大きく変化し、目に見えない抽象的な概念を理解することが求められるようになります。
算数では、それまでの足し算・引き算といった単純な計算から、小数や分数、図形の概念など、イメージを膨らませながら考える必要のある内容へと移行します。文章問題も増え、単なる計算力だけでなく、状況を正確に把握し、適切な解法を選ぶ思考力が必要になってきます。
理科でも電気や水の状態変化など、目に見えないものや日常生活では体験しにくい現象を学ぶ機会が増えます。論理的に考え、因果関係を理解することが求められるため、思考の過程で混乱する子どもも少なくありません。
この時期は脳の発達により抽象的思考が育ち始める時期ですが、個人差も大きく現れます。そのため、学習内容の変化についていけない子どもがつまずきを感じることになるのです。
語彙力・読解力の不足が影響する
9歳の壁では、語彙力や読解力の不足が学習のつまずきを引き起こす大きな要因となります。中学年になると、国語の教科書に登場する文章は長く複雑になり、日常生活ではあまり使わない語彙も増えてきます。
説明文では、身近ではないテーマについても読み解く必要が出てきます。たとえば「葛藤」など、普段なじみのない言葉が出てくることで、文章全体の理解が難しくなることもあります。読解力が不足していると、文章の意図を正確に捉えられず、問題の本質を見誤ってしまうことがあるでしょう。
特に重要なのは、この読解力の不足が国語だけでなく、他の教科にも影響を及ぼす点です。算数の文章題が解けない原因は、計算力ではなく問題文を正確に理解できていないことにあるケースが多いのです。理科や社会でも、教科書の説明を正しく理解できなければ、知識の吸収が困難になります。
このように、語彙力・読解力の不足は学習全般のつまずきにつながるため、9歳の壁の重要な原因の一つといえるでしょう。
自己認識の変化による影響
9歳頃になると、子どもは自分自身を客観的に見る力が発達し、周囲と比較して自分の位置づけを認識できるようになります。これは成長の証ですが、同時に学習面での自信喪失につながることもあります。
この時期の子どもは、「自分は勉強が得意・不得意」といった意識が芽生え始めます。小学校低学年の頃は親からの励ましで素直に頑張れていたのに対し、中学年になると周囲と自分を客観的に比較するようになり、「自分は頭が良くない」「他の子よりできない」と悲観的に考えやすくなります。
抽象的な学習内容が増え、理解が難しくなることも相まって、自己評価が下がる子どもも少なくありません。自分に対する自信が低下すると、学習への意欲も減退し、さらなるつまずきを招く悪循環に陥ることもあります。
文部科学省の資料でも、この時期は「自己に対する肯定的な意識を持てず、劣等感を持ちやすくなる時期」と指摘しています。自己認識の変化は、9歳の壁において子どもの学習意欲や取り組む姿勢に大きな影響を与える重要な要因なのです。
9歳の壁で生じる変化

「9歳の壁」を迎えると、子どもたちの内面や対人関係、生活環境などさまざまな面で変化が現れます。脳の発達により自分を客観的に見る力が育ち、友人との関係性も深まるこの時期。環境の変化も相まって、子どもたちは大きな転換期を迎えることになります。
ここでは、9歳の壁で生じる主な変化と、子どもたちが抱える課題について解説します。
自分を客観視できるようになり、劣等感を抱きやすくなる
9歳頃になると、子どもたちは物事を対象化して認識する力が育ち、自分自身を客観的に見られるようになります。文部科学省の資料でも、この時期は「自分のことも客観的にとらえられるようになる」と説明されています。
自分と他者を比較して、「自分はこれが得意」「あの子はあれが上手」と認識できるようになる一方で、劣等感を抱きやすくなるという側面もあります。特に学習面での差が見えてくると、「自分は頭が良くない」「他の子よりできない」などと悲観し、自己評価を下げてしまうことがあります。
心の成長としては重要な段階ですが、発達の個人差も顕著になる時期であるため、自己肯定感を持ちにくくなることも。子どもの反応はさまざまで、内に閉じこもる子もいれば、他人への嫉妬から無視や嫌がらせをする子もいます。ネガティブな感情との付き合い方を学ぶことが重要な時期といえるでしょう。
友人関係が深まる一方で、トラブルも増える
小学校3~4年生になると、友人関係にも大きな変化が訪れます。低学年の頃は「家が近い」「席が隣」といった偶然の要素で友達になることが多かったのに対し、この時期になると気が合う子同士でグループを作り、友達との関係性が深まるようになります。
関係が深くなる一方で、閉鎖的な仲間集団となってトラブルが生じることも増えてきます。グループ内での同調圧力が生まれたり、小さな行き違いから仲間はずれが起きたりすることもあるのです。
友人との衝突は辛い経験ですが、人間関係の構築に必要な社会性を身につける大切な機会でもあります。しかし、この時期の子どもはまだ感情のコントロールが未熟なため、トラブルを上手く解決できずに悩みを抱え込むことも少なくありません。子どもの様子をよく観察し、必要に応じて大人がサポートする姿勢が求められるでしょう。
友人関係の変化により、親との関係性も変わる
友人関係が深まることで、親子関係にも変化が生まれます。それまでは親と過ごす時間を何より大切にしていた子どもも、9歳頃になると友人との時間を優先するようになることが増えてきます。
また、この時期の子どもは親に秘密を作り始めるようになります。特に9歳の壁特有の劣等感や友達関係のトラブルについては、親に相談せず自分で抱え込むことも多くなります。これは子どもなりの自立の表れでもありますが、保護者としては子どもの内面や考えが見えづらくなり、子育ての悩みが増えることにもなるでしょう。
相談相手が親から友達へと移行していくことは自然な成長過程ですが、重要なのは子どもが困った時に頼れる存在であり続けること。親子のコミュニケーションの取り方を工夫し、信頼関係を保ちながら子どもの自立を見守る姿勢が大切になります。
放課後の居場所がなくなり、孤独を感じやすくなる
9歳頃になると、放課後の過ごし方にも変化が生じます。小学校4年生頃からは、それまで利用していた学童保育から卒業することが多くなります。特に共働き家庭では、子どもが放課後をどこで過ごすかが課題となることがあります。
子どもたちは自宅で一人で過ごす時間が増えることで、孤独感や不安感を抱えることがあります。また、自己管理が十分にできない場合、勉強や生活習慣に影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
放課後の居場所が減ることで、親としても「9歳の壁」に直面する子どもの過ごし方について悩むことが多くなります。クラブ活動や習い事などで新たな居場所を見つけることもできますが、それぞれの子どもの特性や興味に合わせた環境づくりが求められます。子どもが安心して過ごせる場所を確保することは、9歳の壁を乗り越える上で重要な要素となるのです。
9歳の壁でつまずきやすい科目

9歳の壁の時期には、学習内容の変化により特定の教科でつまずきやすくなります。低学年では具体的な理解や単純な暗記で対応できた学習内容が、中学年になると抽象的な概念理解や思考力を必要とするものへと変わっていきます。
教科ごとにどのような変化があり、どんな点でつまずきやすいのか、解説します。
算数|計算から論理的思考へ
小学校4年生になると、算数の学習内容は大きく変化します。それまでの足し算や引き算、九九といった比較的単純な計算問題から、より複雑な思考を要する内容へと移行するのです。
図形や小数、分数、グラフなど、目に見えにくい概念の理解が必要になる単元が増えてきます。たとえば、小数や分数の考え方は抽象的であり、具体的なイメージを持ちにくいため、理解に苦しむ子どもも少なくありません。
また、文章問題も増加し、問題文の内容を正確に読み取り、適切な解法を選択する思考力が求められるようになります。単なる計算力だけでは対応できず、「なぜそうなるのか」という論理的な思考プロセスが重要になってくるのです。
算数は積み上げ式の教科であるため、一度つまずくと、その後の学習にも影響が出やすいという特徴があります。どこでつまずいているのかを見極め、基礎からしっかり理解することが重要な科目といえるでしょう。
国語|文章を正しく理解する力が必要に
国語においても、9歳の壁の時期にはつまずきやすい変化が見られます。説明文などで、日常生活ではあまり触れない題材や身近ではないテーマの文章を読み解くことが求められるようになります。
語彙に関しても「葛藤」など、普段なじみのない言葉が出てくることが増え、文章の理解がしづらくなるケースが増えてきます。文章が長くなり、構成も複雑になるため、要点を捉える力や、文章全体の流れを把握する力が必要になるのです。
また、問いに対して適切に答えるためには、文章の表面的な理解だけでなく、書かれていない内容を推測したり、筆者の意図を汲み取ったりする力も求められるようになります。こうした読解力は、国語だけでなく他の教科の学習にも大きく影響するため、この時期の国語のつまずきは全体の学力低下につながることもあります。
国語でつまずいた場合は、文章を読む習慣をつけたり、分からない言葉は辞書で調べる癖をつけたりすることで、少しずつ改善していくことが大切です。
理科・社会|因果関係を理解する力が必要に
理科や社会の学習内容も、9歳の壁の時期に大きく変化します。理科では電気や水の状態の変化など、目に見えない現象や直接体験することが難しい内容が増えてきます。
目に見えなかったり、イメージしづらかったりする学習内容は、子どもたちの理解を難しくします。また、単に現象を知るだけでなく、「なぜそうなるのか」という因果関係を論理的に考えることが求められるようになるため、思考の途中で混乱してしまうケースもあります。
社会においても、低学年の身近な地域の学習から、より広い視野での地理や歴史、政治などの学習へと発展していきます。表面的な知識だけでなく、社会の仕組みや歴史的背景などを関連づけて理解することが必要になってきます。
両教科とも論理的思考力が求められるため、単なる暗記ではなく「なぜそうなるのか」を考える習慣を身につけることが大切です。子どもの「なぜ?」という疑問を大切にし、一緒に考える姿勢でサポートしていくことが効果的でしょう。
英語|ルールの理解と応用が求められる
多くの小学校で外国語活動が本格的に始まるのもこの時期です。初めのうちは歌やゲームなど楽しみながら英語に触れる活動が中心ですが、徐々に単語や簡単な表現を覚える必要が出てきます。
初めて触れる言語であるため、発音や文字の読み方など、日本語とは異なるルールに戸惑う子どもも少なくありません。また、文法や会話のパターンを理解し、それを応用する力も求められるようになってきます。
英語の学習では、聞く・話す・読む・書くという4つの技能をバランスよく身につける必要がありますが、どれか一つでもつまずくと、英語全体に対する苦手意識を持ってしまうことがあります。
新しい言語の習得には個人差が大きいため、子どものペースに合わせて楽しく継続できる環境を整えることが重要です。英語の歌を聴いたり、簡単な会話を日常に取り入れたりすることで、無理なく英語に親しむ機会を作ることがおすすめです。
9歳の壁を乗り越えるために親ができるサポート方法

子どもが9歳の壁に直面したとき、親のサポートは非常に重要です。子どもの成長に寄り添い、適切な支援を行うことで、この時期の壁を乗り越える力を育むことができます。
以下では、家庭でできる具体的なサポート方法をご紹介します。
「わからない」を見逃さない
9歳の壁の時期には、学習内容が抽象的になり、つまずくポイントが増えてきます。子どもが「わからない」と感じている部分を見逃さず、サポートすることが大切です。
特に算数のような積み上げ式の教科では、一度つまずくとその後の学習にも影響が出やすいため注意が必要です。子どもがどこまで理解していて、どこからわからなくなっているのかを一緒に探り、基礎からしっかり理解できるようサポートしましょう。
具体的な学習内容は、できるだけイメージしやすいように具体例を挙げたり、図や映像を活用したりすると効果的です。たとえば、「0.5」や「1/2」は「どちらも半分だね」と身近な言葉で解説するだけでも、子どもの理解は深まります。つまずきには復習と反復学習が重要なので、理解が定着するまで根気強くサポートしましょう。
読解力を鍛える習慣をつける
9歳の壁の時期に国語でつまずくと、他の教科にも影響が出やすくなります。文章の読解力を高めることは、すべての学習の基盤となるため、日常生活の中で読解力を鍛える習慣をつけることが効果的です。
読書の習慣をつけることは、語彙力や読解力を高める最も基本的な方法です。子どもの興味に合わせた本を選び、一緒に読書の時間を持つことも良いでしょう。また、読んだ本の内容について話し合うことで、理解力や表現力も育ちます。
日常の会話でも、「なぜそう思うの?」と子どもの考えを引き出す質問をしたり、ニュースや出来事について話し合ったりすることで、考える力や表現する力を養うことができます。読解力は一朝一夕には身につきませんが、日々の積み重ねが大きな力になることを意識してサポートしましょう。
成功体験を積み重ねる
9歳の壁にぶつかると、自信を失い自己評価が下がりやすくなります。この時期の子どもには、自信を回復させるために成功体験を積み重ねることが非常に重要です。
子どもが「できること」「できたこと」を具体的に認め、褒めることで、長所に気づき、自信を取り戻せるようサポートしましょう。ただなんとなく褒めるのではなく、「すごい」「さすが」などの言葉と共に、何がよかったのかを具体的に伝えることがポイントです。時には第三者の言葉による間接的な褒め言葉も効果的です。
「できないこと」については、どうすればできるようになるかを一緒に考え、努力する姿勢を伝えましょう。小さな成功体験を重ねることで、子どもは徐々に自信を取り戻し、前向きな気持ちで学習に取り組めるようになります。
勉強のやり方を工夫する
9歳の壁の時期には、放課後の居場所の変化や学習内容の高度化により、勉強のやり方を工夫することも必要になってきます。家での学習環境を整え、効果的な勉強法を身につけられるようサポートしましょう。
イライラやモヤモヤが晴れない時は、気分転換として家事を手伝ってもらったり、本や映画に触れたり、自然体験をしたりすることも有効です。家族からの感謝を受け取ることで自己肯定感を高めたり、学校や友人関係とは異なる世界に触れることでリフレッシュできることもあります。
また、子どもの興味・関心を生かした学習方法を取り入れると、意欲的に取り組めることが多いです。得意な分野から学習を始め、徐々に苦手分野にも取り組むなど、子どものペースに合わせた学習計画を立てることで、無理なく継続できる習慣づくりをサポートしましょう。
塾を活用するメリット

9歳の壁を乗り越えるためには、家庭でのサポートに加えて、専門的な学習指導を受けることも効果的な選択肢となります。塾では学校とは異なる環境で、子どもの特性や課題に合わせた指導を受けることができます。
特に学習内容が複雑になるこの時期に、塾を活用することで得られるメリットについて見ていきましょう。
つまずきに応じた個別指導が受けられる
9歳の壁の時期は、学習内容の複雑化により、子どもそれぞれが異なるポイントでつまずくことが多くなります。塾では、こうした個々のつまずきに応じたきめ細かい指導を受けることが可能です。
学校の授業は集団で進みますが、塾、特に個別指導塾では子どもの理解度や進捗に合わせて学習を進めることができます。つまずいている単元を見極め、基礎からしっかり理解できるよう丁寧に教えてもらえる点は大きな強みです。
また、担任の先生だけでは対応しきれない部分も、塾の先生に相談することで解決の糸口が見つかることもあります。子どもの「わからない」を放置せず、早めに解消することで、学習の遅れを取り戻し、自信を取り戻す助けになるでしょう。
双方向型授業で考える力を伸ばせる
9歳の壁を超えるためには、暗記だけでなく「考える力」を育むことが重要です。塾では双方向のやりとりを通じて、この思考力を伸ばす指導が受けられます。
子どもが質問しやすい環境で、「なぜそうなるのか」「どうしてこの解き方になるのか」を考えながら学ぶことで、単なる答えの暗記ではなく、本質的な理解へとつながります。特に算数や理科など、論理的思考が必要な教科では、考えるプロセスを重視した指導が効果的です。
また、塾では学校とは違う教え方や教材に触れることで、多角的な視点が身につきます。同じ内容でも別の切り口から学ぶことで、理解が深まることもあるでしょう。こうした思考力の育成は、9歳の壁を乗り越えるだけでなく、将来的な学力の基盤となる重要な要素です。
学習の習慣づけができる
9歳の壁の時期には、学習内容が増え、自己管理能力も求められるようになります。塾に通うことで、定期的な学習リズムが身につき、家庭での学習習慣の定着にもつながります。
塾では週に数回の授業に加え、宿題や予習・復習の課題が出されることが一般的です。これにより、計画的に学習を進める習慣が自然と身についていきます。「いつ」「何を」学習するかが明確になるため、子ども自身も見通しを持って取り組めるようになるでしょう。
また、同じ目標を持った仲間と一緒に学ぶことで、競争心や向上心も芽生えます。「友達も頑張っているから自分も頑張ろう」という意識は、学習意欲を高める大きな要因となります。このように、塾を活用することで学習習慣の確立を支援し、自律的に学ぶ力を育てることができるのです。
エディック創造学園の小学生講座のご紹介


エディック創造学園は、兵庫県内で50年以上にわたり子どもたちの学力向上をサポートしてきた実績ある学習塾です。「合格力×人間力」を教育理念に掲げ、単なる受験対策だけでなく、時代の変化に対応できる力を育成します。国語力を重視した体系的カリキュラムと対面・オンラインのハイブリッド学習を提供し、県内難関校への高い合格実績を誇ります。
AIなどのテクノロジーの進歩により、さまざまな変化が急速に起こる不確実な時代、子どもたちに求められるのは経験やデータに基づいて考える力です。エディック創造学園の「ELEMENTARY LESSON」では、変化の激しい時代を生き抜くための真の「考える力」を養います。9歳までの子どもに特化したレッスンで、抽象的思考力と「イメージング力」を重視。脳の発達が著しい時期に「聞く・読む・話す・書く」を鍛え、将来の学習基盤を構築します。
特に9歳の壁を乗り越えるための「玉井式国語的算数教室®」や「玉井式 魔法の国語®」など、独自のプログラムを導入しています。
エディック創造学園「ELEMENTARY LESSONS」の特徴を詳しく見る
玉井式学習プログラムを活用し、子どもの学びをサポートしよう

エディック創造学園では、9歳の壁を乗り越えた先にある受験対策も万全です。厳しい研修を積んだ講師陣が、わかりやすい授業と子どもたちに寄り添う熱意で確かな学力を育みます。集団指導でも一人ひとりを大切にし、小さな成長も見逃さない細やかな指導が特徴です。
オリジナル教材や「LCC学力循環向上システム」によって、授業で学んだ内容を家庭学習や確認テストで定着させ、理解不足は個別にケアする体制を整えています。
また、「デイリースタディ」や「がんばりカップ」など、子どもたちのやる気を引き出す仕組みも充実。自ら学ぶ意欲を高め、成長を褒めたたえることで「もっとやりたい!」という気持ちを育みます。
9歳の壁を乗り越え、自信をもって学ぶために
9歳の壁は子どもの成長過程で避けて通れない発達段階ですが、適切なサポートがあれば乗り越えられる壁です。この時期は抽象的思考が育ち始め、自分を客観視できるようになる重要な転換点。学習内容が複雑化し、友人関係も深まる中で、子どもたちは新たな課題に直面します。親御さんは子どもの「わからない」を見逃さず、読解力を高める習慣づけや成功体験の積み重ねを意識したサポートを心がけましょう。
塾の活用も効果的な選択肢の一つです。エディック創造学園では、9歳までに伸ばすべき「イメージング力」や「読解力」を鍛える玉井式を採用。子どもの自己肯定感を高める指導で、9歳の壁を乗り越え、その先の学びにも自信を持って取り組める力を身につけられるよう導きます。