- 公開日2025/04/08
- 最終更新日2025/04/08
双方向型授業とは?オンライン授業の形式と特徴を解説

目次
新型コロナウイルス禍を機に広く導入されたオンライン授業。その中でも「双方向型授業」という言葉をよく耳にしませんか?一方通行のオンデマンド型とは異なり、教師と生徒がリアルタイムで意見交換できる双方向型授業には、どのような特徴があるのでしょうか。
「授業についていけるか不安」「集中力が続くか心配」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、双方向型授業には疑問をその場で解決できる、教師が理解度に合わせて進められるなど、従来の対面授業に近い形でオンラインの利便性を享受できるメリットがあります。
本記事では、双方向型授業の特徴やメリット・デメリット、効果的な活用法を徹底解説します。これを読めば、あなたに合ったオンライン授業の形式を選び、効率的な学習環境を整えるヒントが得られるでしょう。
双方向型授業とは

双方向型授業とは、生徒と講師がリアルタイムでやり取りしながら進行するオンライン授業の形式のひとつです。近年、オンライン授業が普及し、さまざまな学習スタイルが生まれていますが、その中でも双方向型授業はとくに「対話型学習」や「アクティブラーニング」に適していると言われています。
オンライン授業には主に 双方向型、オンデマンド型 という2つの種類があり、それぞれ学習の進め方や適した学習者の特性が異なります。本章では、まずオンライン授業の種類について整理し、その後、双方向型授業の特徴を詳しく解説します。
オンライン授業の種類
オンライン授業は大きく分けて「双方向型授業」と「オンデマンド型授業」の2つに分類されます。
双方向型授業(ライブ配信型)は、ZoomやGoogle Meetなどのウェブ会議システムを利用して、教師と生徒がリアルタイムで映像や音声データをやり取りしながら授業を進める形式です。同じ時間を共有するため、対面に近い感覚で授業を受けられるのが特徴です。質問やディスカッションをその場で行うことができます。
一方、オンデマンド型授業は、あらかじめ録画された授業動画を学習者が好きなタイミングで視聴する形式です。時間や場所に縛られず、自分のペースで学習を進められる利点があります。また、理解できなかった部分を繰り返し視聴することも可能です。
双方向型授業とは
双方向型授業とは、教師と生徒がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら進める授業形式です。従来の一方向型授業では教師から生徒への知識伝達が中心でしたが、双方向型授業では生徒が意見を発信する機会が多く設けられています。
Zoomなどのウェブ会議システムを活用し、教師と生徒がインターネットを通じて集まり、映像や音声でリアルタイムにやり取りします。教師が説明するだけの一方向型と、教師と生徒が話し合いながら進める形式があり、後者では生徒の主体的・能動的な学習を促進します。
双方向型授業の最大の特徴は、疑問点をその場で質問できることです。教師も生徒の表情や反応を見ながら、理解度に合わせて授業のペースや内容を調整できます。また、グループワークや小グループでの交流も可能で、生徒同士の学び合いを実現できます。
この授業形式は「主体的・対話的で深い学び」(アクティブラーニング)を実現する手段として注目されています。生徒が自らの意見を発信し、他者と対話することで思考を深め、単なる知識の習得を超えた学びへと発展させることが期待されています。オンライン環境であっても、活発なディスカッションや意見交換により、対面授業に近い学習体験を提供できるのが双方向型授業の大きな魅力です。
双方向型授業の特徴
双方向型授業の最大の特徴は、そのリアルタイム性にあります。教師と生徒が同じ時間を共有し、即時的なやり取りが可能となります。ZoomやGoogle Meetなどのウェブ会議システムを使用することで、対面授業と同様の臨場感を持ちながら授業を受けられます。
質疑応答が活発になるのも大きな特徴です。生徒はわからない点をその場で質問でき、教師もすぐに回答することで学習の効率が高まります。また、チャット機能を活用して文字でのやり取りも可能なため、発言が苦手な生徒も参加しやすい環境が整います。
さらに、グループワークやディスカッションが取り入れやすい点も特徴的です。ブレイクアウトルーム機能などを使用して少人数のグループに分かれ、意見交換や共同作業を行うことができます。これにより生徒同士の相互学習が促進されます。
一方向型授業では教師から生徒への一方的な知識伝達が中心となり、生徒は受動的な立場になりがちです。双方向型授業では生徒が能動的に授業に参加するため、集中力が持続しやすく、理解度も高まります。また、教師は生徒の理解度を確認しながら授業を進められるため、学習内容の定着度も向上します。
双方向型授業が活発な理由
双方向型授業が活発になる最大の理由は、生徒の参加意欲を高める仕組みが組み込まれている点です。従来の一方向型授業では生徒は聞き手に徹していましたが、双方向型授業では意見を求められる機会が多く、自ら考え発言する必要があります。このような能動的な学習姿勢は、知識の定着と思考力の向上に効果的です。
講師からの即時フィードバックも大きな要因です。生徒の発言や回答に対して教師がすぐに反応し、評価や補足説明を加えることで、生徒は自分の理解度を確認できます。「この部分はよく理解できている」「ここはもう少し考え直した方がいい」といった具体的なフィードバックにより、学習の方向性が明確になります。
さらに、新型コロナウイルス禍以降の教育スタイルの変化も、双方向型授業の活性化に寄与しています。緊急的に導入されたオンライン授業が次第に洗練され、教師も生徒もオンラインでのコミュニケーション技術を習得してきました。当初は対面授業の代替手段と見なされていましたが、今では対面授業では実現できない利点も広まっています。
双方向型授業のメリット

双方向型授業には、従来の一方向型授業やオンデマンド型授業にはない様々なメリットがあります。教師と生徒がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら授業を進めることで、学習効果を高め、より充実した教育環境を実現することができます。ここでは、双方向型授業の主な3つのメリットについて詳しく解説していきます。学習の質を向上させるこれらの特徴を理解することで、より効果的な学習方法を選択する手がかりになるでしょう。
生徒の理解度向上
双方向型授業の最大のメリットは、生徒の理解度が向上することです。従来の一方向型授業では、生徒が内容を理解できなくても授業は進行していき、わからないままになってしまうことがありました。しかし、双方向型授業では、生徒がリアルタイムで質問できるため、疑問点をその場で解決できます。
特にオンラインでの双方向型授業では、チャット機能を使って質問することも可能なため、発言が苦手な生徒も気軽に質問できる環境が整います。これにより、「質問したいけど手を挙げるのは恥ずかしい」という心理的障壁を下げることができます。
また、教師側も生徒の反応や表情を見ながら授業を進められるため、理解度を確認しつつ授業のペースを調整できます。理解が不十分だと感じれば説明を補足したり、逆に理解が早ければ先に進んだりと、クラス全体の学習効率を高めることができます。
学習意欲を高める
双方向型授業は、生徒の学習意欲を高める効果があります。一方向型授業では生徒は受動的に情報を受け取るだけですが、双方向型授業では自ら考え、発言することが求められるため、能動的な学習姿勢が育まれます。
クラスメイトの意見を聞くことも、大きな刺激になります。様々な視点からの考えに触れることで、「自分はこう思っていたけど、そういう考え方もあるのか」と新たな気づきが生まれます。これは特に社会科や国語などの議論を伴う科目で効果的です。
さらに、教師からの即時フィードバックも学習意欲を高める要因です。自分の発言や回答に対して教師から評価や補足説明があることで、達成感や次への意欲が生まれます。「先生に認められた」という経験は、学習へのモチベーションを大きく向上させます。
講師と生徒のコミュニケーションが密になる
双方向型授業では、講師と生徒のコミュニケーションが密になることで、より個別化された学習支援が可能になります。対面授業と同様に、講師は生徒一人ひとりの表情や反応を見ながら授業を進めることができるため、理解度や学習状況をリアルタイムで把握できます。
とくにオンラインでの双方向型授業では、チャット機能やアンケート機能などを活用することで、従来の対面授業では取りこぼしていた生徒の疑問や意見も拾い上げることができます。全員が同時に回答できるシステムにより、クラス全体の理解度を一目で確認することも可能です。
講師と生徒のコミュニケーションが密になることで、学習進捗の個別管理も容易になります。「この生徒はこの単元が苦手そうだ」「あの生徒は応用問題に挑戦させてみよう」といった判断を、講師がその場でできるようになります。これにより、一人ひとりの学習ペースや特性に合わせた個別フォローが実現します。
双方向型授業のデメリット

双方向型授業には多くのメリットがありますが、実施する上で以下のようないくつかの課題や制約も存在します。これらのデメリットを事前に理解しておくことで、より効果的に双方向型授業を活用することができるでしょう。
- 時間や場所に制限が出る場合がある
- 集中力を保つのが難しい場合も
- 学習ペースがバラバラになりやすい
またこれらのデメリットを把握することで、適切な対策を講じることも可能に。ここでは、双方向型授業の主な3つのデメリットについて詳しく解説し、実際に双方向型授業を選択する際の判断材料を提供します。
時間や場所に制限が出る場合がある
双方向型授業の大きなデメリットは、リアルタイムで行われるため時間的な制約を受けることです。オンデマンド型授業では自分の好きな時間に学習できますが、双方向型授業では決められた時間に参加する必要があります。これは仕事や家事、他の予定と両立させる必要がある社会人や親などにとって、大きな障壁となる可能性があります。
例えば、授業が平日の昼間に設定されていると、働いている人は参加が難しくなります。また、時差のある海外にいる場合は、深夜や早朝の時間帯になってしまう可能性も。このように時間の固定は、学習の自由度を下げる要因となります。
さらに双方向型授業は、インターネット環境が安定している場所で受ける必要があります。移動中や電波の弱い場所では、授業に支障が出る恐れも。また、カメラやマイクをオンにして参加することが求められる場合、周囲の環境によっては参加が難しいこともあるでしょう。
集中力を保つのが難しい場合も
双方向型授業では、長時間にわたって画面を見続けることで生徒の集中力が途切れやすくなるというデメリットがあります。通常の対面授業でも集中力の持続は課題ですが、オンライン環境ではさらに難しくなる傾向があります。とくに画面上では教師の存在感が薄れがちで、生徒が画面の外で他のことをしていても気づかれにくいという問題も生じます。
さらに、自宅などのプライベート空間で授業を受けることで、周囲の誘惑に負けやすくなる点もあげられます。テレビやゲーム、スマホなどが身近にある環境では、教室のような規律ある空間と比べて気が散りやすくなります。教室の雰囲気や臨場感、緊張感がないと集中できない学習者にとって、これは大きな壁となるでしょう。
学習ペースがバラバラになりやすい
双方向型授業のもう一つの課題は、生徒によって学習ペースや理解度が異なるため、クラス全体の進行管理が難しくなる点です。教師が全員の理解度に合わせようとすると、授業のペースが遅くなったり、カリキュラムが予定通り終わらなかったりする可能性があります。
例えば、理解の早い生徒にとっては授業のペースが遅すぎると感じられ、逆に理解に時間がかかる生徒にとっては速すぎると感じられることも。この場合、どちらかの生徒グループが不満を感じる結果となります。また、質問が多い生徒がいると、その対応に時間を取られ、授業全体の進行に影響することもあります。
双方向型授業では、教師は生徒の理解度を確認しながら臨機応変に対応する必要がありますが、すべての生徒に満足のいく授業を提供することは容易ではありません。カリキュラムの網羅と、生徒一人ひとりの理解度への配慮のバランスを取ることが求められます。
双方向型授業が向いている人とは

双方向型授業は誰にでも同じように効果があるわけではありません。学習スタイルや性格、学習環境によって、より大きな効果を得られる人とそうでない人がいます。ここでは双方向型授業が、とくに効果的な以下の3つのタイプの学習者について詳しく解説します。
- 自発的に学ぶ意欲のある人
- 複数人でのディスカッションや意見交換が得意な人
- 一方向型の授業に集中できない生徒
自分や子どもがどのタイプに当てはまるかを知ることで、より適切な学習方法を選択する手助けになるでしょう。適切な学習環境を選ぶことは、学習効率と学習満足度を大きく高める重要な要素です。
自発的に学ぶ意欲のある人
双方向型授業は、自発的に学ぶ意欲のある人にとくに効果的です。一方向型授業やオンデマンド型授業では、教師から一方的に知識が伝えられるため、生徒側に積極性がなくても授業を受けることができます。しかし双方向型授業では、生徒からも意見を発することが期待されており、生徒の積極性が授業の質に大きく影響します。
自ら進んで考える力を持つ生徒は、双方向型授業で能力を発揮しやすくなります。授業中に質問を投げかけられたとき、自分の意見を持ち、それを表現できる生徒は、双方向型授業の恩恵を最大限に受けることができます。また、わからないことがあればすぐに質問できる姿勢も重要です。授業中にリアルタイムで疑問を解消できるため、理解度が高まります。
複数人でのディスカッションや意見交換が得意な人
双方向型授業は、ディスカッションや意見交換を重視する授業形態であるため、他者との対話が得意な人にとくに向いています。授業中に活発な意見交換が行われることで、多角的な視点から学習内容を捉えることができ、理解が深まります。
他の生徒の意見を聞き、それに対して自分の考えを述べることができる人は、双方向型授業で大きな学習効果を得られます。とくに、「ソクラティック・メソッド」と呼ばれる問答形式の授業では、教師が質問を投げかけ、生徒が返答するというプロセスを通じて知識を深めていきます。このような授業形式は、対話を通じて思考を深めることができる生徒に適しています。
また、グループワークなどの協働学習が含まれる双方向型授業では、他の生徒と協力して課題に取り組む能力が求められます。コミュニケーション能力や協調性が高い生徒は、こうした活動を通じて学びを最大化できるでしょう。オンラインでのグループワークでは、ブレイクアウトルーム機能を使って少人数のグループに分かれ、意見交換や共同作業を行うことが一般的です。
一方向型の授業に集中できない生徒
一方向型の授業では集中力を維持するのが難しい生徒にとって、双方向型授業は大きな助けとなります。長時間にわたって一方的に話を聞き続けることは、多くの人にとって困難なものです。とくに活動的な性格の生徒や、視覚的・体験的な学習スタイルを持つ生徒にとって、一方向型授業は退屈に感じられがちです。
双方向型授業では、生徒が授業に参加する機会が多くあります。質問に答えたり、意見を述べたり、グループディスカッションに参加したりする活動が含まれるため、ずっと受動的に聞いているだけではありません。こうした能動的な参加が、集中力の維持につながります。
また、教師とのリアルタイムのやり取りがあることで、「次は自分が指名されるかもしれない」という適度な緊張感が生まれ、注意力が高まります。これはとくに、ある程度の外部からの刺激がないと集中できない生徒にとって効果的です
さらに、オンデマンド型授業では、動画を一時停止したり、後で見ようと先延ばしにしたりすることが容易ですが、双方向型授業ではリアルタイムで進行するため、こうした先延ばし行動が防げます。決まった時間に授業に参加する必要があるというスケジュールの制約が、逆に学習の規律を守る助けになるのです。
オンラインにおける双方向授業のポイント

オンライン環境で双方向授業を行う際には、対面授業とは異なる特有の課題や注意点があります。効果的なオンライン双方向授業を実現するためには、技術的な準備はもちろん、コミュニケーション方法の工夫も重要です。
ここでは、オンライン双方向授業を成功させるための主なポイントを3つの観点から解説します。適切な準備と理解があれば、オンライン環境でも質の高い双方向授業を実現することができるでしょう。
オンライン双方向授業の特徴と注意点
オンライン双方向授業を効果的に行うためには、まず適切な機材の準備が不可欠です。安定したインターネット環境、パソコンやタブレット、カメラ、マイクなどが基本的に必要となります。とくにライブ配信型の双方向授業では、映像や音声データを大量にやり取りするため、通信環境の質が授業の質に直結します。
接続トラブルへの対策も重要なポイントです。授業中に通信が途切れたり、映像や音声が乱れたりすると、学習の流れが中断され、集中力が低下します。このようなトラブルを最小限に抑えるためには、Wi-Fi環境を整え、可能であればパソコンで授業を受けることが推奨されます。また、授業開始の10〜20分前には接続状態を確認し、余裕を持ったスケジュールで臨むことが大切です。
オンライン授業用のアプリやツールの使い方にも慣れておく必要があります。ZoomやGoogle Meetなどのウェブ会議システムは、事前にインストールし使い方を理解しておくことで、授業開始時のトラブルを防げます。初めて使用する場合は、とくに時間に余裕を持って準備することをおすすめします。
複数人での授業は難しいことも
オンラインでの複数人参加型の双方向授業では、円滑なコミュニケーションを実現するのが難しい場合があります。対面授業では自然に行われる目線のやり取りや表情の読み取り、発言のタイミングの調整などが、オンライン環境では制限されます。
例えば、グループディスカッションを行う際、誰が次に発言するかの合図が伝わりにくく、発言が重なったり、逆に誰も話し始めないという沈黙が生まれたりすることがあります。また、画面越しでは細かな表情や反応が見えづらいため、相手の理解度や感情を把握しにくいという課題もあります。
このような課題に対処するためには、コミュニケーションの工夫が必要です。例えば、「手を挙げる」機能やチャット機能を活用して発言の意思表示をしたり、発言順を事前に決めておいたりする方法があります。また、小グループに分けて議論する「ブレイクアウトルーム」機能を活用することで、より活発な意見交換が可能になります。
スムーズに授業を受けるためのポイント
オンラインの双方向型授業をスムーズに受けるためには、適切な学習環境の整備が不可欠です。まず、静かで集中できる場所を確保することが重要です。家族の会話や生活音、テレビの音などが入らない環境が理想的です。難しい場合は、ヘッドセットを使用することで周囲の音を遮断し、授業に集中しやすくなります。
事前準備も授業の質を左右する重要な要素。バッテリー残量やインターネット接続状況なども事前にチェックしておくべきポイントです。長時間の授業の場合は、電源アダプターを接続しておくなどの対策も忘れないようにしましょう。また、できれば有線LANを使用するか、安定したWi-Fi環境で受講することが望ましいです。
オンライン授業では誘惑に負けてしまうリスクも考慮する必要があります。スマートフォン、ゲーム機、本などの気が散る原因となるものは、授業中は手の届かない場所に置いておくのがよいでしょう。リビングなど家族が見える場所で受講することで、適度な緊張感を保ちながら集中して授業に参加できます。
エディック創造学園のオンライン講座のご紹介

エディック創造学園のオンライン校では、長田高校 人文・数理探究類型、神戸高校、兵庫高校、市立西宮高校、小野高校、加古川東高校、姫路西高校 国際理学科など、トップ校への合格実績を誇ります。
これらの実績は、双方向型オンライン授業による質の高い指導と、50年以上にわたって蓄積された入試データに基づく的確な進路指導の成果です。エディックオンライン校では、高校入試を見据えた特進講座や英検®対策講座など、お子様の志望校合格を強力にサポートする様々な講座を開講しています。
オンライン講座で受験対策するならエディックにお任せ
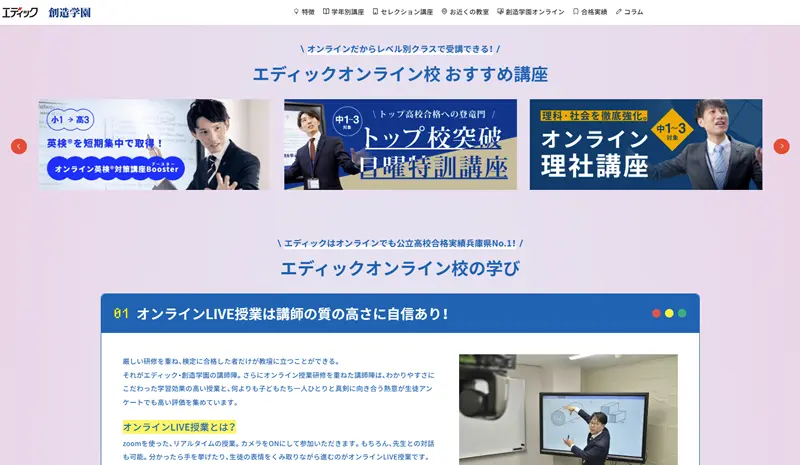
エディックオンライン校では、Zoomを活用したリアルタイム双方向授業で、対面授業と変わらない高品質な指導を提供しています。カメラをONにした授業で表情を見ながら進めるため、生徒の理解度に合わせたきめ細やかな指導が可能です。
また、学習支援アプリ「ロイロノート」も導入し、小テストや宿題の提出・採点をスムーズに行い、一人ひとりの学習状況を丁寧に管理しています。とくに兵庫県の公立高校入試対策では、内申点対策として学校別の定期テスト対策を実施。神戸新聞社と共催の「兵庫統一模試」で実力を確認しながら、保有する膨大な入試データを活用した精密な進路指導も行います。
通塾時間が不要で勉強に集中できるオンライン授業で、志望校合格への最短ルートを提案します。
エディックのオンライン講座で新しい学びをスタートしよう!
これまで解説してきたように、双方向型授業は生徒と講師がリアルタイムでコミュニケーションを取りながら進める学習形式で、対面授業に近い臨場感と学習効果が得られます。その場で質問ができ、講師からの即時フィードバックも受けられるため、理解度の向上や学習意欲の維持に大きく貢献します。
エディック創造学園のオンライン校では、こうした双方向型授業のメリットを最大限に活かした指導を提供しています。Zoomを活用した質の高いライブ授業で、講師が生徒一人ひとりの表情や反応を見ながら進めるため、理解度に応じたきめ細やかな指導が可能です。また、ロイロノートなどの学習支援ツールも導入し、効果的な課題提出や採点フィードバックを実現しています。
双方向型授業の特長を理解し、自分に合った学習環境を選ぶことが学習成果を高める重要な一歩です。エディック創造学園のオンライン講座で、時間と場所を有効活用しながら、効率的で質の高い学びをスタートしてみませんか?





