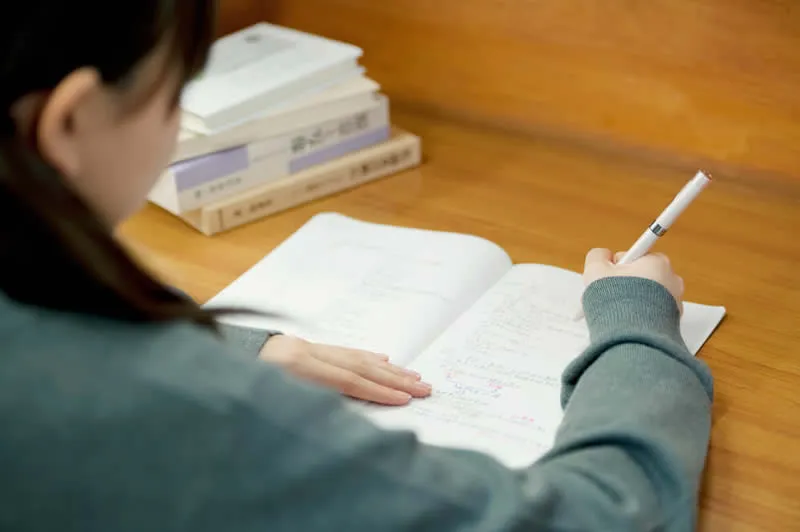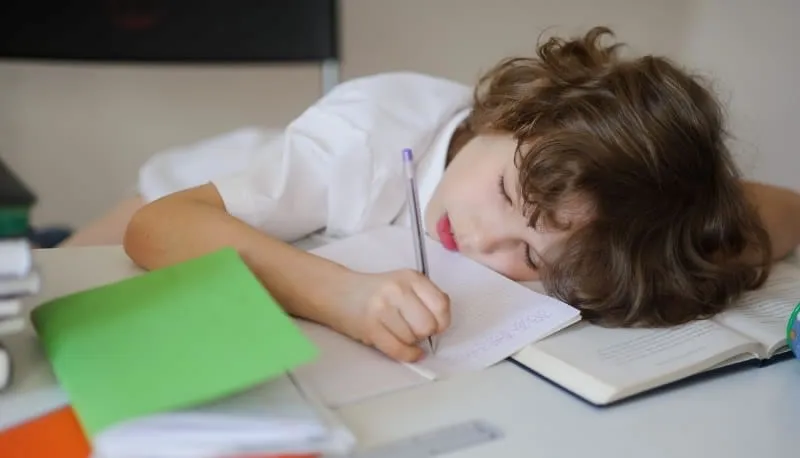- 公開日2024/12/24
- 最終更新日2024/12/24
【エディックの受験生に聞く】受験勉強のやる気がないときモチベを爆上げさせる8つの方法
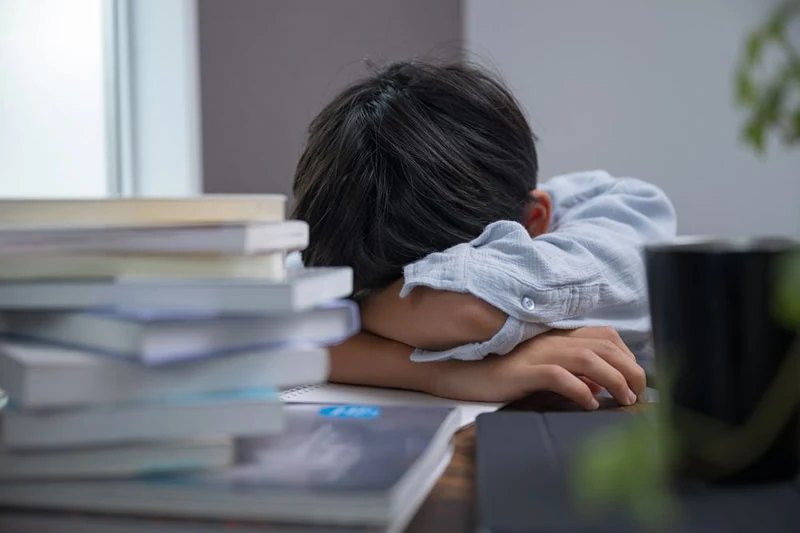
目次
受験勉強に取り組む中で、「やる気が出ない…」と悩むことは誰しも経験するものです。しかし、そんなときにどのようにモチベーションを上げ、再び集中して勉強に取り組むかが合格へのカギとなります。 本記事では、やる気が出ない原因を解説し、エディックの受験生たちから得た、やる気を爆上げするための具体的な8つの方法を紹介します。学習環境や勉強の進め方を見直し、モチベーションを保ちながら受験勉強を進めるヒントをお伝えします。
そもそも勉強のやる気がでない原因とは

受験勉強中にやる気が出ないという悩みを抱える高校生は少なくありません。その原因は単一ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているのが特徴です。
体調面では睡眠不足や運動不足、栄養バランスの乱れなどが、集中力低下やモチベーション不足につながることがあります。メンタル面では、勉強に対する不安や焦り、他の悩みごとなどが要因となっています。
また、周囲の騒音や机の散らかり具合といった環境的な問題、効果的な学習方法がわからないといった技術的な課題も、学習意欲の低下を引き起こします。長期戦となる受験勉強では、これらの要因が重なり合って深刻な学習意欲の低下を招くことも。まずは自分の中で何が原因なのかを見極めることが、解決への第一歩となります。
受験に対して目標が明確になっていない
受験勉強に対するモチベーションが上がらない最大の要因として、目標が明確になっていないことが挙げられます。「なんとなく勉強しなければ」という漠然とした意識や、「周りが勉強しているから」という同調圧力だけでは、継続的な学習意欲を維持することは困難です。
目標が不明確なまま時間だけが過ぎていくと、自分が何のために勉強しているのかわからなくなり、学習に対する意味を見失ってしまいます。とりわけ受験勉強は長期的な取り組みが必要なため、明確な目標がないと途中で挫折してしまう可能性が高まります。
効果的な目標設定には、合格後の具体的な未来像を思い描くことが重要です。「志望校でどのような学問を探求したいか」「将来どんな仕事に就きたいか」といった大きな目標から、「サークル活動を楽しみたい」「学食のグルメを堪能したい」といった身近な目標まで、自分なりの明確なビジョンを持つことが大切です。
志望校のパンフレットやホームページを定期的にチェックしたり、オープンキャンパスに参加したりすることで、目標をより具体的にイメージすることができます。明確な目標を持つことで、現在の自分の立ち位置と目標とのギャップが見えてきます。このギャップを埋めるために必要な努力が具体化されることで、自然と学習への意欲も高まってくるはずです。
勉強方法がわからず前進している感覚がない
効率的な学習方法を見出せていないことは、モチベーション低下の大きな要因となっています。「何から手をつければよいのかわからない」「どのように時間配分すべきか迷う」といった状況では、せっかく机に向かっても成果を実感できず、次第にやる気を失ってしまいます。
受験勉強では、限られた時間の中で広範囲の学習内容を効率よく習得する必要があります。しかし、多くの生徒が具体的な学習方法を確立できないまま、手探りの状態で勉強を続けています。このような状況では、努力の割に成績が伸びず、モチベーションの低下を招くという悪循環に陥りやすくなります。
この課題を解決するには、まず学校の先生や塾の講師など、経験豊富な指導者に相談することが有効です。プロフェッショナルからのアドバイスを得ることで、自分に適した効果的な学習方法を見つけることができます。また、学習計画を立てる際は、達成可能な小さな目標を設定し、一つずつクリアしていくアプローチが効果的です。
日々の進捗を記録に残し、目に見える形で確認できるようにすることも重要です。「今日は英単語を50個覚えた」「この章の問題が全て解けるようになった」といった具体的な成果を実感することで、着実に前進している手応えを得ることができます。
頑張って勉強しても模試やテストで望む点数が取れない
真面目に勉強に取り組んでいるにもかかわらず、模擬試験やテストの結果が思うように伸びないことは、モチベーション低下の深刻な要因となります。限られた時間の中で成果を出さなければならない受験生にとって、努力が点数に反映されないことは大きなストレスとなります。
しかし、学習の成果が目に見える形で現れるまでには、一定の時間が必要です。特に受験勉強では、基礎的な知識の積み重ねが重要であり、その過程で一時的に成績が伸び悩む「プラトー期」を経験することは珍しくありません。
重要なのは、日々の学習の積み重ねを可視化し、小さな進歩を実感できるような工夫をすることです。例えば、解けなかった問題が解けるようになった、暗記すべき項目を完璧に覚えられたなど、些細な成長も見逃さず記録に残していきましょう。
また、定期的に弱点を分析し、効率的な復習方法を見直すことで、より確実な実力向上を図ることができます。
一時的な点数にとらわれすぎず、長期的な視点で自身の成長を評価することが大切です。日々の努力は必ず実を結ぶものであり、プラトー期を乗り越えた先には大きな成長が待っているはずです。
同級生やライバルと比較して劣等感や不安を感じてしまう
受験期において深刻な心理的負担となるのが、周囲との比較による劣等感です。かつては同程度の成績だった同級生の成長ぶりを目の当たりにし、自分だけが取り残されているような不安を感じることは少なくありません。
このような比較意識は、「自分には能力がない」という否定的な自己評価につながりやすく、学習意欲を著しく低下させる原因となります。また、「このままでは志望校に合格できないのではないか」という不安が日増しに募り、精神的な疲労も蓄積していきます。
この状況を改善するためには、他者との比較ではなく、自分自身の成長に焦点を当てることが重要です。例えば、1ヶ月前の自分と比べてどれだけ知識が増えたか、どの分野の理解が深まったかといった、自己の進歩を振り返ることで、着実な成長を実感することができます。
また、適度な競争意識は学習意欲の向上につながりますが、過度な比較は逆効果となります。互いに励まし合える仲間を見つけ、良好な関係性の中で切磋琢磨することで、健全なモチベーションを維持することができるでしょう。自分のペースを大切にしながら、着実に前進することを心がけましょう。
勉強のやる気がないときでも集中できる4つの方法

勉強のやる気が出ない状況は、誰にでも起こりうる自然な現象です。しかし、受験勉強においては、そのような状況でも効率的に学習を進めていく必要があります。
やる気の有無に関わらず集中して勉強に取り組むためには、いくつかの実践的な方法があります。例えば、学習環境を変えることで気持ちを切り替えたり、適度な運動で心身をリフレッシュしたり、勉強する科目を変更したり、短時間の仮眠を取り入れたりすることで、集中力を取り戻すことができます。
これらの方法は、多くの受験生が実践し、効果を実感している対処法です。ここでは、やる気が出ないときでも集中して勉強を継続できる具体的な方法を4つご紹介します。
学習環境に変化をつける
学習環境の変化は、気持ちの切り替えに大きな効果をもたらします。いつもと同じ環境で勉強を続けていると、慣れによる気の緩みや飽きが生じやすく、集中力が低下してしまいます。
まずは自分の勉強机から見直してみましょう。散らかった机の上を整理整頓するだけでも、心理的なリセット効果が期待できます。また、スマートフォンなどの気が散る要素は視界から遠ざけ、必要な教材だけを机の上に置くことで、集中しやすい環境を整えることができます。
さらに効果的なのが、勉強する場所を変えてみることです。図書館や自習室は、静かな環境と適度な緊張感があり、集中力を高めるのに適しています。また、周りにも勉強している人がいることで、自然とモチベーションが上がります。カフェで勉強するのも一案です。適度な背景音や心地よい空間で、リラックスしながら学習に取り組むことができます。
自宅で勉強する場合でも、いつもとは違う場所を活用してみましょう。リビングや和室など、普段は使わない場所で勉強することで、新鮮な気持ちで学習に臨むことができます。季節や天候が良ければ、ベランダや庭で勉強するのも気分転換になります。
学習環境を整える際は、照明や室温、換気にも注意を払いましょう。明るすぎず暗すぎない適度な明るさ、快適な室温、新鮮な空気は、集中力の維持に重要な要素です。これらの環境要因を整えることで、より効率的な学習が可能となります。
身体を動かしてリフレッシュする
長時間同じ姿勢で勉強を続けることは、体の疲労だけでなく、精神的な疲れも蓄積させます。そんなとき効果的なのが、適度な運動を通じたリフレッシュです。特に散歩は、新鮮な空気を吸いながら気分転換できる最適な運動方法です。
20分程度の軽い運動は、脳内の血流を改善し、集中力の回復を促進します。また、自然と触れ合うことで、ストレス解消にも効果があります。運動の際は、勉強のことは一旦忘れ、周囲の景色を楽しんだり、深呼吸をしたりしながら、心身をリラックスさせることが大切です。
運動の方法は散歩に限りません。自宅でできる簡単なストレッチや、その場でのジャンプなど、自分に合った運動を選びましょう。大切なのは、激しすぎない程度の運動を選ぶことです。過度な運動は逆に疲労を招き、その後の学習効率を下げてしまう可能性があります。
特に効果的なのが、朝の運動です。朝日を浴びながら体を動かすことで、体内時計が整い、一日の学習に向けて良好なコンディションを作ることができます。また、午後の眠気を感じる時間帯にも、短時間の運動を取り入れることで、集中力を回復させることができます。
運動後は、水分補給を忘れずに行いましょう。適度な水分補給は、脳の働きを活性化させ、学習効率の向上にもつながります。また、運動と水分補給を組み合わせることで、より効果的なリフレッシュが期待できます。
勉強している科目を変えてみる
同じ科目を長時間学習し続けることは、脳の疲労を招き、学習効率の低下につながります。やる気が出ないと感じたときは、勉強する科目を変更することで、新たな気持ちで学習に取り組むことができます。
効果的な科目の切り替え方として、暗記系の科目から計算系の科目へ、あるいは読解系の科目へと移行する方法があります。これは、脳の異なる部分を使うことで、特定の部分への負担を分散させる効果があります。例えば、英単語の暗記に行き詰まりを感じたら、数学の問題演習に切り替えるといった具合です。
また、得意科目と苦手科目をバランスよく配置することも重要です。得意科目に取り組むことで自信を回復し、その勢いで苦手科目に挑戦するという流れを作ることができます。ただし、苦手科目を後回しにしすぎないよう注意が必要です。
時間帯によって学習する科目を固定するのも効果的です。午前中は計算力を必要とする数学、午後は読解力を要する国語というように、時間帯に応じて科目を決めておくことで、学習リズムが作りやすくなります。
さらに、各科目の学習時間にメリハリをつけることも大切です。1科目あたり30分から1時間程度を目安に区切り、短い休憩を挟みながら科目を切り替えていくことで、効率的な学習が可能になります。
20分程度の仮眠をとる
疲労や睡眠不足が原因でやる気が出ない場合、20分程度の仮眠が効果的な解決策となります。この時間設定には科学的な根拠があり、20分程度の仮眠は、深い睡眠に入りすぎることなく、脳を適度にリフレッシュさせる効果があります。
仮眠のタイミングとして最適なのは、午後1時から3時の間です。この時間帯は人間の体内時計の関係で自然と眠気を感じやすく、短時間の仮眠を取ることで、その後の学習効率を大幅に向上させることができます。
ただし、仮眠時間が長すぎると逆効果となる可能性があります。30分以上の睡眠は深い睡眠段階に入ってしまい、起床時に強い睡眠慣性(目覚めの悪さ)を感じる原因となります。また、夜の睡眠にも影響を及ぼす可能性があるため、適切な時間管理が重要です。
仮眠を効果的に取るためのコツとして、タイマーを設定することが推奨されます。また、横になる前に水を一杯飲んでおくと、適度な時間で自然と目が覚めやすくなります。仮眠後は、顔を洗う、軽いストレッチをするなどして、スムーズに学習モードに戻れるよう工夫することも大切です。
夜更かしによる睡眠不足を仮眠で補おうとするのは望ましくありません。基本的な生活リズムを整え、十分な夜間睡眠を確保したうえで、あくまでもリフレッシュの手段として仮眠を活用することが重要です。
受験勉強のモチベーションを保って継続的に勉強できる4つの方法

受験勉強は長期戦です。一時的なやる気だけでなく、継続的にモチベーションを維持していくことが合格への重要なカギとなります。
しかし、日々の学習を続けていく中で、誰しもモチベーションの波を経験するものです。そこで重要になってくるのが、学習意欲を持続させるための具体的な方策です。目標設定の工夫や、小さな達成感の積み重ね、周囲のサポートの活用など、様々な方法を組み合わせることで、安定した学習モチベーションを保つことができます。
ここでは、多くの受験生が実践し、効果を実感している4つの方法をご紹介します。これらの方法を自分の状況に合わせて取り入れることで、受験勉強を最後まで継続する力を身につけることができるでしょう。
勉強の目的・受験の目標を明確に定める
受験勉強を継続的に進めていく上で、最も重要なのが明確な目的意識を持つことです。志望校合格という大きな目標は、日々の学習を支える強い原動力となります。しかし、単なる「合格したい」という漠然とした思いだけでは、持続的なモチベーションを維持することは困難です。
効果的なのは、合格後の具体的な未来像を思い描くことです。「大学でどのような学問を探求したいか」「どんな研究に取り組みたいか」「将来はどんな職業に就きたいか」など、志望校合格後のビジョンを具体的にイメージすることで、目標達成への意欲が高まります。
オープンキャンパスへの参加は、そうしたビジョンを具体化する絶好の機会となります。実際のキャンパスの雰囲気を体感し、在学生の話を聞くことで、自分の将来像がより鮮明になります。また、大学の施設や設備を見学することで、「ここで学びたい」という意欲も一層強くなるでしょう。
志望校のパンフレットやホームページを定期的にチェックすることも効果的です。興味のある学部や研究室の情報、カリキュラムの詳細、キャンパスライフの様子など、具体的な情報に触れることで、目標に向かう原動力が生まれます。
目標設定の際は、「なぜその大学に行きたいのか」「その大学で何を得たいのか」という本質的な問いかけも大切です。表面的な理由ではなく、自分の価値観や将来の夢と結びついた目標であれば、より強い意志を持って勉強に取り組むことができます。
短期目標とご褒美を決める
志望校合格という大きな目標に向かって進んでいく中で、日々の小さな目標設定も重要な役割を果たします。長期的な目標だけでは達成までの道のりが遠く感じられ、モチベーションを維持することが難しくなりがちです。そこで効果を発揮するのが、短期目標の設定です。
短期目標は、具体的で達成可能な内容に設定することが重要です。例えば、「今週は英単語を100個覚える」「今日は数学の問題集を3章分終わらせる」といった具体的な目標を立てることで、達成への道筋が明確になります。この際、自分の実力や生活リズムを考慮し、無理のない目標設定を心がけましょう。
目標達成時には、自分へのご褒美を用意することも効果的です。好きなお菓子を食べる、映画を観る、趣味の時間を持つなど、自分が楽しみにできる報酬を設定することで、学習への意欲が高まります。ただし、ご褒美は適度な範囲に留め、次の学習に支障が出ないよう注意が必要です。
進捗管理も重要な要素です。日々の学習内容や達成状況を記録することで、自分の成長を目に見える形で確認することができます。進捗管理には、手帳やスマートフォンのアプリなど、自分に合った方法を選びましょう。
小さな目標を達成していく過程で得られる成功体験は、学習意欲の維持に大きく貢献します。一つ一つの達成感を積み重ねることで、大きな目標への確かな一歩を踏み出すことができます。
応援してくれる人や尊敬する人の存在を意識する
受験勉強は時として孤独な戦いに感じられますが、実際には多くの人があなたの挑戦を支えています。家族、先生、友人など、日々応援してくれる人々の存在を意識することは、モチベーション維持の大きな力となります。
特に家族の支援は何物にも代えがたい励みとなります。学費を工面してくれる両親、勉強に集中できる環境を整えてくれる家族の存在を忘れずに。また、丁寧な指導をしてくれる先生方、共に頑張る友人たちの存在も、学習意欲を高める重要な要素です。
偉人や著名人の名言を活用するのも効果的です。自分の心に響く言葉を見つけ、机の前に貼っておいたり、スマートフォンの待ち受け画面にしたりすることで、やる気が下がったときの心の支えとなります。ただし、過剰なプレッシャーにならないよう、自分を励ましてくれる前向きな言葉を選びましょう。
また、同じ目標に向かって頑張る仲間の存在も大きな励みとなります。互いの進捗を共有したり、悩みを相談し合ったりすることで、モチベーションを高め合うことができます。時には息抜きとして、将来の夢を語り合うのも良いでしょう。
このように、周囲のサポートを積極的に活用することで、より強い意志を持って学習に取り組むことができます。自分は決して一人ではないという認識が、困難を乗り越える力となるのです。
他人と成績を比較しない
受験期における大きな落とし穴の一つが、他人との過度な比較です。周囲の成績が気になり、自分の位置づけばかりを考えてしまうと、本来の目標を見失ってしまう恐れがあります。受験は本質的に自分との戦いであり、他人の成績に一喜一憂することは、かえって学習の妨げとなります。
大切なのは、自分の成長に焦点を当てることです。例えば、先月の模試と比べてどの程度点数が伸びたか、以前は解けなかった問題が解けるようになったかなど、自分自身の進歩に目を向けましょう。小さな成長を認識し、それを喜ぶ気持ちを持つことが、継続的な学習意欲につながります。
適度な競争意識は学習の原動力となりますが、それは他者との比較ではなく、目標に向かって切磋琢磨する関係であるべきです。良きライバルの存在は、互いの成長を促進する要因となります。
また、成績の伸び方は人それぞれです。ある人は急激な成長を見せ、またある人は緩やかな進歩を遂げます。自分のペースを守り、着実に前進することが、最終的な目標達成への近道となります。
日々の学習記録をつけることで、自分の成長を可視化することも効果的です。他人と比較するのではなく、自分の努力の軌跡を振り返ることで、確かな手応えを感じることができるでしょう。
どうしても受験勉強のやる気がでないときは進学塾を検討するのもあり

受験勉強のモチベーション維持に悩む方には、エディック創造学園の充実した学習サポートがおすすめです。兵庫県公立高校入試合格実績No.1※の実績を誇る当塾では、単なる受験指導にとどまらない、合格力と人間力を育む独自の教育システムを展開しています。
特に注目すべきは、全教科の基礎となる「国語力」の徹底的な強化です。読解力を高める多読指導や、入試に必須の速読力を養成するカリキュラムにより、確実な学力向上を実現しています。また、習熟度別のクラス編成と反転授業システムにより、一人ひとりの理解度に合わせた効果的な学習が可能です。
さらに、エディック創造学園では、やる気を引き出すユニークな取り組みも実施しています。第一線で活躍するスペシャリストによる講演会や、オンラインツアーなど、知的好奇心を刺激するイベントを通じて、学習意欲の向上を図っています。
定期テスト対策も万全で、学校別の出題傾向を分析した専門的な指導により、内申点アップをサポート。加えて、通塾とオンラインを組み合わせたハイブリッド学習により、効率的な学習環境を提供しています。
やる気の出ない時期こそ、プロフェッショナルのサポートを受けることで、モチベーションを取り戻し、志望校合格への確かな一歩を踏み出すことができます。
勉強のやる気をコントロールして受験を制そう!
受験勉強において、やる気の波は避けられないものです。しかし、それをうまくコントロールし、最終的な目標である志望校合格を勝ち取るためには、効果的なサポート体制が重要となります。
一人で受験勉強に取り組むと、モチベーションの維持が難しく、学習効率も上がりにくいものです。そんなとき、エディック創造学園の「合格力×人間力」を重視した指導アプローチが、大きな力となります。まず特筆すべきは、5教科すべての基盤となる「国語力」の徹底的な強化です。読解力を磨く多読指導から、入試で必須となる速読力の養成まで、体系的なカリキュラムで確実な学力向上を実現します。
また、学習意欲を高める独自の取り組みも充実しています。第一線で活躍する専門家による講演会やオンラインツアーなど、知的好奇心を刺激するイベントを通じて、学ぶ意欲を自然と引き出します。さらに、習熟度別クラス編成と反転授業システムにより、一人ひとりの理解度に合わせた効果的な学習が可能です。
兵庫県公立高校入試合格実績No.1※の実績が示す通り、エディック創造学園では、単なる受験指導にとどまらない、実績と信頼の指導力で、確実な志望校合格へと導きます。やる気の維持に悩む受験生の皆さんも、ぜひエディック創造学園の充実したサポート体制を活用し、合格への確かな一歩を踏み出してみませんか。