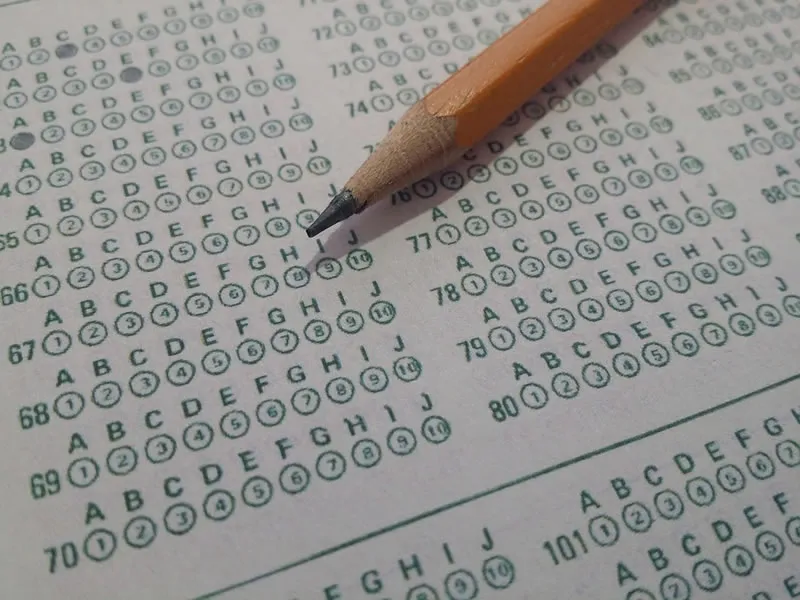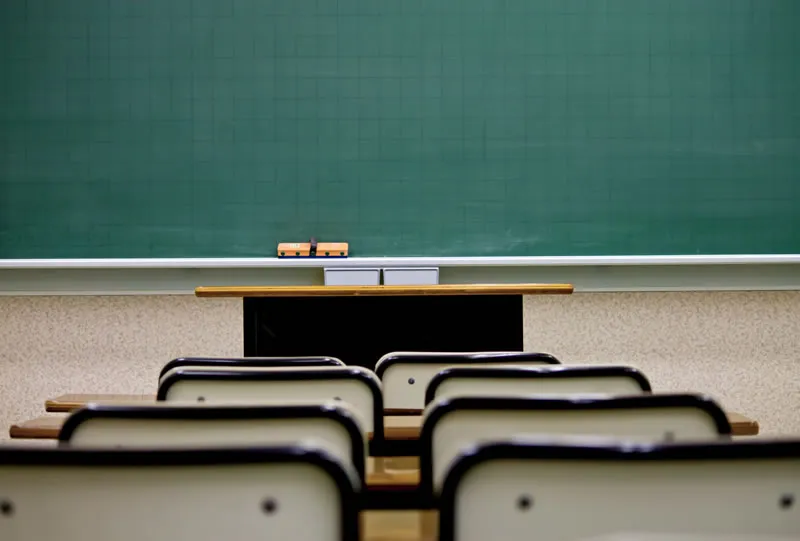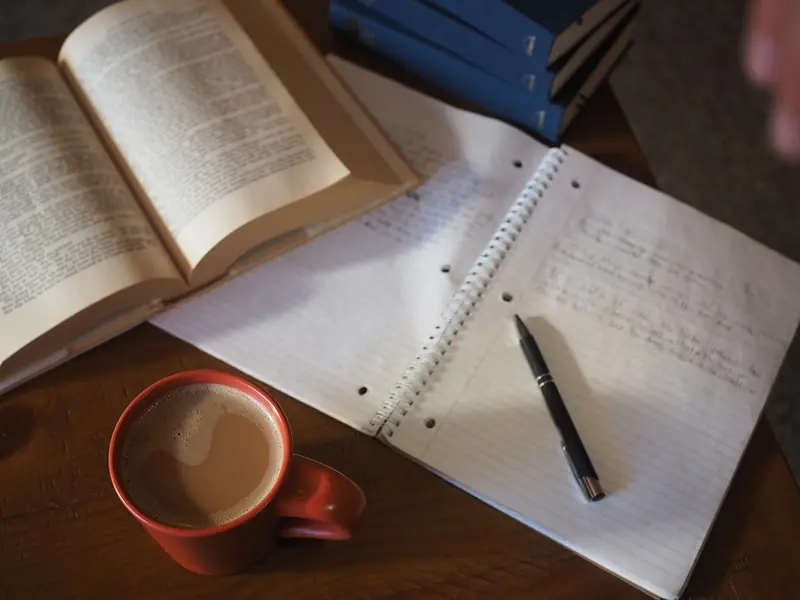- 公開日2025/01/21
- 最終更新日2025/01/21
中学生が勉強しない理由とその対策を解説。保護者ができるサポート方法とは?

目次
勉強へのモチベーションを失った中学生に、親としてどのように接すれば良いか悩んでいませんか?成績の低下や進路の心配が尽きない一方で、反抗期によるコミュニケーションの難しさも壁となりがちです。
このコラムでは、中学生が勉強しない理由を深掘りし、その状況を打破する具体的なアプローチ方法を解説します。親子の絆を再構築しながら、勉強への意欲を引き出すためのヒントが満載なので是非参考にしてください。
中学生が勉強しないのはなぜ?

中学生が勉強に向き合えない状況は、多くの保護者様が直面する悩みです。しかし、ただ「勉強しなさい」と声をかけても、かえって反発を招くことも。効果的なサポートをするために、まずは勉強しない理由を理解することが重要です。ここでは、勉強しない理由を知る重要性と、主な理由について解説します。
勉強しない理由を知る重要性
中学生時代の学習習慣は、将来に大きな影響を与えます。勉強しない状態を放置すると、まず目の前の定期テストや高校受験に影響が出るだけでなく、学習内容が理解できないまま進級することで、さらに勉強から遠ざかってしまう負のスパイラルに陥るリスクがあります。
また、基礎学力が不足したまま高校に進学すると、授業についていけなくなる可能性も高まります。中には、学習意欲の低下から不登校になってしまうケースも。勉強しない理由を理解し、適切なサポートを行うことで、このような事態を防ぐことができます。
中学生が勉強しない5つの主な理由
中学生が勉強しない理由は以下の通りです。それぞれの理由について補足します。
勉強の必要性を感じていない
勉強する意義を実感できない場合、子どもは「なぜ勉強するのか」という疑問を抱きます。親がその意義を示し、子どもの未来に直結することを説明する必要があります。
集中力が続かない
成長期特有の特性として、注意力が分散しやすいことが挙げられます。勉強に集中できる環境づくりや、短時間で達成できる目標設定が有効です。
成績が伸びないと感じる
努力が結果につながらないと、やる気を失う子どもも少なくありません。この場合、学習方法を見直し、小さな成功体験を積み重ねることが必要です。
生活リズムが乱れている・疲れている
部活動や人間関係のストレスが原因で、生活リズムが崩れることがあります。規則正しい生活をサポートすることが、勉強の継続につながります。
スマートフォンやゲームなどの誘惑
スマートフォンやゲームに時間を費やすことで、勉強への集中力が削がれます。しかし、これらを完全に禁止するのではなく、適切なルールを設けて活用する方法を模索することが大切です。
勉強しない中学生にどうアプローチするか

中学生の勉強に関する問題は、一朝一夕には解決できません。ただ叱責したり、強制的に勉強させたりするのではなく, 子どもの心理に寄り添った適切なアプローチが必要です。ここでは、保護者ができる具体的な行動と、子どもと一緒に考えるべきことについて解説します。
親が取るべき具体的な行動
まず大切なのは、子どもが勉強しない状況に対して冷静に向き合うことです。感情的な叱責や他の子との比較は、かえって子どもの学習意欲を低下させる原因となります。代わりに、子どもの現状を客観的に把握し、学習環境の整備から始めましょう。
例えば、勉強に集中できる静かな場所を確保したり、スマートフォンなどの誘惑を適切に管理したりすることが有効です。また、子どもの小さな進歩や努力を見逃さず、積極的に褒めることで自己肯定感を育むことも重要です。子どもが「やればできる」という実感を得られれば、自然と学習意欲は高まっていきます。
子どもと一緒に考えるべきこと
効果的なアプローチのためには、子どもと対話しながら具体的な学習計画を立てることが重要です。例えば、1日の勉強時間や休憩のタイミング、スマートフォンの使用ルールなどを、子ども自身の意見を聞きながら決めていきましょう。
また、勉強に向き合えない背景には、友人関係や部活動でのストレス、将来への不安など、様々な要因が隠れている可能性があります。定期的な対話を通じて、子どもの悩みや不安を理解し、必要に応じて適切なサポートを検討することが大切です。
このような対話を重ねることで、子どもは「親は自分の味方である」という安心感を得られ、前向きに勉強に取り組めるようになっていきます。
学年別の中学生が勉強しない理由

中学生が勉強しない理由は、学年によって大きく異なります。環境の変化や心理的な成長、直面する課題によって、各学年特有の悩みや問題が存在します。効果的なサポートを行うためには、学年ごとの特徴を理解することが重要です。ここでは、各学年の特徴的な理由について詳しく見ていきましょう。
中学1年生
中学1年生の時期は、環境の大きな変化に直面する時期です。中学受験を経験した生徒の場合、過酷な受験勉強の反動で「燃え尽き症候群」に陥ることがあります。長期間の緊張から解放され、学習意欲が急激に低下してしまうのです。
また、高校受験までまだ時間があるため、勉強に対する危機感が薄いことも特徴です。新しい環境での人間関係づくりや部活動に意識が向きがちで、勉強への優先順位が下がりやすい時期でもあります。さらに、授業内容の急激な難化に戸惑い、学習意欲を失ってしまうケースも少なくありません。
中学2年生
中学2年生になると、学校生活に慣れすぎてしまい「中だるみ」が起こりやすい時期です。部活動が本格化し、練習や試合で忙しくなることも、勉強時間の確保を難しくする要因となっています。多くの生徒が、部活動と勉強の両立に悩むことになります。
部活動では上級生としての責任も増え、精神的・肉体的な負担も大きくなります。帰宅後は疲れて勉強に向かう気力が残っていない、という状況に陥りやすいのです。また、学校生活に慣れたことで適度な緊張感が失われ、だらけた生活習慣になってしまうケースも見られます。
中学3年生
中学3年生は、受験への不安やプレッシャーが大きな影響を与える時期です。「勉強しなければ」という焦りを強く感じる一方で、そのプレッシャーが重くのしかかり、かえって勉強から逃避してしまうことがあります。
また、将来の目標が明確に定まっていない生徒の場合、「何のために勉強するのか」という根本的な疑問に悩み、学習意欲を失ってしまうことも。特に中高一貫校の生徒は、高校受験という明確な目標がないため、学習へのモチベーションを維持することが難しい場合があります。
勉強しない理由別の解決策5選

中学生が勉強しない理由は、個々の状況によって異なります。そのため、効果的な解決策も、その理由に応じて変えていく必要があります。ここでは、主な理由別に具体的な解決策を紹介します。お子様の状況に最も近いものを参考に、適切なサポートを考えていきましょう。
勉強の必要性を感じていない場合
勉強の必要性を感じていない場合、まずは将来についての対話から始めることが重要です。「勉強しなさい」という一方的な押し付けや「将来困るから」という抽象的な説明では、お子様の心に響きません。
代わりに、お子様の興味や関心に耳を傾け、将来の夢や目標について一緒に考える時間を設けましょう。この対話を通じて、子どもは自分の将来像を具体的にイメージできるようになり、そこに向かうために必要な学びの意義を見出すことができます。
例えば、お子様が好きなことと将来の職業を結びつけ、そのために必要な学力について話し合うことで、自然と学習意欲が芽生えてきます。たとえばゲームが好きな子には「ゲームクリエイターには数学や英語が必要」、スポーツが好きな子には「スポーツトレーナーには生物の知識が重要」というように、具体的に説明することが効果的です。
また、部活の先輩や身近な大人の経験談を聞く機会を作ったり、実際の職場を見学したりすることで、勉強の意義をより実感的に理解できるようになります。このように、子どもの興味関心に寄り添いながら、学ぶことの意味を一緒に探っていくことが大切です。
集中力が続かない場合
集中力が続かないケースでは、無理に長時間の学習を強いるのではなく、短時間の学習を効果的に組み合わせる方法がおすすめです。特に効果的なのが「ポモドーロ・テクニック」と呼ばれる時間管理法です。人間の集中力には波があり、長時間同じことを続けることは誰にとっても難しいものです。むしろ、短い時間で区切って集中と休憩を繰り返すことで、より効率的な学習が可能になります。
25分の学習と5分の休憩を1セットとし、これを繰り返す方法です。集中できる時間は個人差があるため、お子様の場合は15分学習・5分休憩など、柔軟に調整するとよいでしょう。タイマーを使って時間を区切ることで、「この時間だけ頑張ろう」という気持ちが生まれやすくなります。
また、休憩時間には軽い体操や深呼吸を取り入れたり、水分を補給したりすることで、次の学習に向けてリフレッシュできます。慣れてきたら徐々に学習時間を延ばしていき、最終的には自分に合った理想的な学習サイクルを見つけることができるでしょう。
成績が伸びないと感じる場合
成績が思うように伸びず、やる気をなくしているケースでは、まずは達成可能な小さな目標から始めることが大切です。例えば、「次のテストで5点上げる」「今日は数学の問題を3問解く」「英単語を5つ覚える」といった、具体的で実現可能な目標を設定します。大きすぎる目標は挫折を招きやすいため、最初は確実に達成できる水準に設定することが重要です。
小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできる」という自信が芽生え、より大きな目標にも挑戦できるようになっていきます。また、努力の過程を認め、小さな進歩も見逃さず褒めることで、学習意欲を高めることができます。
例えば「問題を最後まで解こうと頑張ったね」「計算ミスが減ってきたね」など、具体的な改善点を指摘して褒めることで、子どもは自分の成長を実感できます。目標を達成したときは、家族で祝うなど、達成感を共有することも効果的です。このような積み重ねが、学習への前向きな姿勢を育てていきます。
生活リズムが乱れている・疲れている場合
部活動や不規則な生活で疲れが蓄積している場合、まずは基本的な生活リズムの改善が必要です。文部科学省の「早寝早起き朝ごはん」国民運動によると、中学生の望ましい睡眠時間は8時間以上とされています。成長期の中学生にとって、質の良い睡眠は心身の健康維持に不可欠であり、学習効率にも大きく影響します。
まずは就寝時間と起床時間を固定し、十分な睡眠時間を確保しましょう。就寝前2時間はスマートフォンやゲームを控えるなど、良質な睡眠のための工夫も大切です。
また、朝食をしっかり取り、栄養バランスの取れた食事を心がけることも重要です。特に脳の働きを活発にするたんぱく質や、集中力を高めるビタミン類を意識的に摂取することで、学習効率が向上します。生活リズムが整うことで、自然と学習に向かう体力と気力が生まれてきます。
休日の過ごし方も含めて、無理のない生活パターンを一緒に考えていきましょう。部活動との両立が難しい場合は、朝型の生活リズムに切り替えて朝学習を取り入れるなど、柔軟な対応も検討してください。
スマートフォンやゲームの誘惑が強い場合
スマートフォンやゲームの誘惑が強い場合、完全な使用禁止は逆効果になりかねません。デジタル機器は現代の学習ツールとしても活用できる上、友人とのコミュニケーション手段としても重要な役割を果たしているためです。
代わりに、学習時間中はスマートフォンを別室で保管したり、通知をオフにしたりするなど、明確なルールを設定することが効果的です。また、勉強に役立つアプリの活用を検討するなど、デジタル機器を学習のための味方に変える工夫も考えられます。
このルール作りは、お子様と話し合いながら進めることが重要です。「1時間勉強したら15分ゲームができる」「宿題が終わったらSNSの時間を設ける」といった具体的な約束を、お子様自身の意見も取り入れながら決めていきましょう。自分で決めたルールであれば、守る意識も高まります。
また、勉強に集中できる環境作りとして、机の周りには必要な文具以外置かないようにすることも有効です。さらに、保護者自身も子どもと一緒の時間はスマートフォンの使用を控えるなど、良いお手本を示すことで、ルールの定着がスムーズになるでしょう。
勉強しない中学生に効果的なサポート方法

中学生が勉強に向き合えるようになるには、適切な環境づくりと心理的なサポートの両方が重要です。ただ勉強を強制するのではなく、子どもが自発的に学習に取り組める環境を整え、学ぶ意義を実感できるようなアプローチが効果的です。ここでは、特に重要な2つのサポート方法について詳しく解説します。
勉強環境を整える
子どもが集中して勉強できる環境を整えることは、学習習慣を定着させる第一歩となります。理想的な勉強環境には、静かで適度な明るさが保たれた専用のスペースが必要です。できれば個室や仕切られた空間を用意し、勉強に必要な道具を整理して配置しましょう。また、温度や湿度、換気にも気を配り、長時間集中できる快適な環境を整えることが重要です。加えて、姿勢を正しく保てる椅子や、目の高さに合わせた適切な机の高さなど、身体的な負担を軽減する工夫も効果的です。
特に注意したいのが、スマートフォンやゲーム機などの誘惑となるものの管理です。完全な使用禁止は逆効果になる可能性があるため、学習時間中は別室で保管するなど、お子様と相談しながらルールを決めることをおすすめします。また、机の上は必要最小限の文具のみにし、集中を妨げる要素を減らすことも大切です。
さらに、勉強時間と休憩時間を明確に区切り、タイマーなどを活用して時間管理をすることで、メリハリのある学習が可能になります。定期的に環境を見直し、子どもの様子を観察しながら、より良い学習空間づくりを心がけましょう。
勉強する理由を一緒に考える
中学生が勉強に向き合えない大きな要因の一つが、「なぜ勉強をする必要があるのか」という根本的な疑問です。この問いに対して、「将来のため」「いい高校に入るため」という漠然とした説明や、「当たり前でしょう」という押し付けでは、お子様の心には全く響きません。むしろ、そのような一方的な説明は、勉強への抵抗感を強める結果になりかねません。
代わりに、お子様の興味や関心に寄り添いながら、具体的な対話を重ねることが重要です。例えば、好きなことや得意なことを将来の職業とどう結びつけられるのか、そのために必要な学力は何かを一緒に考えます。ゲームが好きな子には、ゲームクリエイターに必要な数学や英語の重要性を、スポーツが好きな子にはスポーツトレーナーに必要な生物や化学の知識について話すなど、子どもの関心に合わせた具体例を示すことが効果的です。
また、部活動の先輩や尊敬する大人の経験談を共有したり、実際に働く現場を見学したりすることで、学ぶことの意義を実感できることもあります。このように、子どもの目線に立った対話を通じて、勉強する意味を見出していくことが大切です。
これはNG!保護者が注意するべきこと

中学生の学習意欲を引き出そうとするあまり、保護者が逆効果な対応をしてしまうケースは少なくありません。子どもの成長にとって重要な時期だからこそ、保護者の適切な関わり方が求められます。ここでは、特に避けるべき対応とその理由について解説します。
子どもを責めすぎない
「なぜ勉強しないの?」「このままじゃダメでしょう」「やる気が足りない」といった責める言葉は、子どもの心に大きな負担を与えます。国立教育政策研究所の調査によると、叱責や非難を受けることで、約7割以上の中学生の学習意欲が低下すると報告されています。特に思春期の中学生は、大人からの否定的な言葉に敏感で、一度心を閉ざしてしまうと、立て直すのに時間がかかってしまいます。
むしろ、勉強から逃避している背景には、授業についていけない不安や、効果的な学習方法がわからないといった具体的な悩みが隠れていることが多いのです。また、友人関係や部活動でのストレス、将来への漠然とした不安など、勉強以外の要因が影響している可能性もあります。
責めるのではなく、まずはなぜ勉強に向き合えないのか、その理由に耳を傾け、子どもの立場に立って一緒に解決策を探ることが重要です。子どもが安心して本音を話せる関係性を築くことで、学習への意欲も自然と芽生えてくるはずです。
参考:国立教育政策研究所『「学習意欲に関する調査研究」概要』
自立を促すサポートに徹する
中学生は自己決定感を強く求める時期です。親が「こうすべき」と細かく指示を出したり、自分の経験に基づいた勉強方法を押し付けたりすることは、かえって子どもの自主性を損なう結果となります。また、過度な干渉は反抗心を引き起こし、学習意欲の低下にもつながりかねません。
重要なのは、子ども自身が「やろう」と思える環境づくりと、適度な距離感を保ったサポートです。例えば、勉強時間や目標設定を子どもに任せ、必要に応じてアドバイスする立場に徹することで、自己決定力と責任感が育ちます。また、子どもが主体的に考えて決めたスケジュールや方法を尊重し、見守る姿勢を保つことも大切です。
うまくいかないときも、すぐに指摘や修正をするのではなく、子ども自身が気づき、改善できるよう導くことが望ましいでしょう。このような経験の積み重ねは、将来的な学習習慣の確立にも大きく貢献し、自立した学習者への成長を促します。
無理な期待を押し付けない
「親の卒業した高校に行ってほしい」「兄弟と同じように成績を取ってほしい」「もっと上位の学校を目指すべき」など、保護者の期待や理想が重圧となり、子どもの学習意欲を削いでしまうことがあります。子どもには一人ひとり異なる成長のペースや、得意・不得意な分野、興味関心の方向性があることを理解する必要があります。また、現代の教育環境は保護者の学生時代とは大きく異なっていることにも注意が必要でしょう。
大切なのは、子どもの現在の状態をありのまま受け入れ、その子なりの成長を温かく支援していくことです。無理な期待や過度なプレッシャーは、親子関係を悪化させるだけでなく、子どもの自己肯定感も著しく低下させてしまい、勉強以外の面でも悪影響を及ぼす可能性があります。
まずは子どもの興味や関心に寄り添い、得意分野を伸ばしながら、その子に合った現実的な目標設定を一緒に考えていく姿勢が重要です。そうすることで、子ども自身が自分のペースで成長していける環境が作れるはずです。
エディック創造学園の中学生講座のご紹介

「勉強しなさい」と言われても、なかなか机に向かえないお子様のために、エディック・創造学園は独自の「やる気」を引き出すシステムを確立しています。
スパイラル学習で確実な理解を促す「LCC学力循環向上システム」により、対面授業での学習、小テストでの理解度確認、個別ケアまでをトータルでサポート。お通いの中学校の定期テスト問題を分析した定期テスト対策授業をはじめ、各教室の自習室やオンライン自習室も開放。内申点アップを目指して、質の高い学習を提供します。
また、現役高校生や大学生との交流イベント「先輩エディック・創造学園に帰る」など、モチベーションを高める楽しい企画も充実。50年以上の実績に基づく、やる気と学力を育む環境で、お子様の確かな成長をサポートいたします。
中学生の学習、高校受験対策ならエディックにお任せ

エディック創造学園では、兵庫県の公立高校入試の特徴を熟知した独自の受験対策システムを展開しています。特に注目すべきは、内申点対策。兵庫県の入試では内申点が合否判定の50%を占めるという特徴があり、定期テスト対策が極めて重要です。
各中学校の出題傾向を徹底分析し、学校別の定期テスト対策を実施。主要5教科はもちろん、内申点に大きく影響する実技教科(音楽・美術・技術家庭・保健体育)までしっかりとサポートします。休日を利用した「猛勉強会」や、オンラインと通塾を組み合わせたハイブリッド学習など、効率的に学力を伸ばすための工夫も満載です。
さらに、50年以上にわたって蓄積した豊富な入試情報と5万人以上の合格実績データを活用し、精度の高い進路指導を実現。神戸新聞社と共催の「兵庫統一模試」など、地域に密着した独自の取り組みも特徴です。生徒一人ひとりの夢の実現に向けて、エディック創造学園は全力でサポートいたします。
中学生のうちから勉強する習慣を育てましょう
中学生の学習意欲を高めるには、一朝一夕の解決策はありません。しかし、原因を理解し、適切なサポートを行うことで、確実に改善への道を開くことができます。
まず大切なのは、なぜ勉強しないのかという根本的な理由を理解すること。スマートフォンなどの誘惑、学習内容の難化、反抗期など、様々な要因が複雑に絡み合っています。その上で、子どもの心理に寄り添いながら、環境整備や適切な声かけを行っていくことが重要です。
エディック創造学園では、50年以上の指導実績から得られたノウハウを活かし、一人ひとりの生徒に合わせた効果的な学習支援を提供しています。通塾とオンラインを組み合わせたハイブリッド学習、やる気を引き出す独自の企画、徹底した定期テスト対策など、生徒の自発的な学習意欲を育む様々な取り組みを行っています。
勉強への取り組み方で悩まれている保護者の方は、ぜひ一度エディック創造学園の無料体験授業をご検討ください。経験豊富な講師陣が、お子様に合った最適な学習方法をご提案いたします。