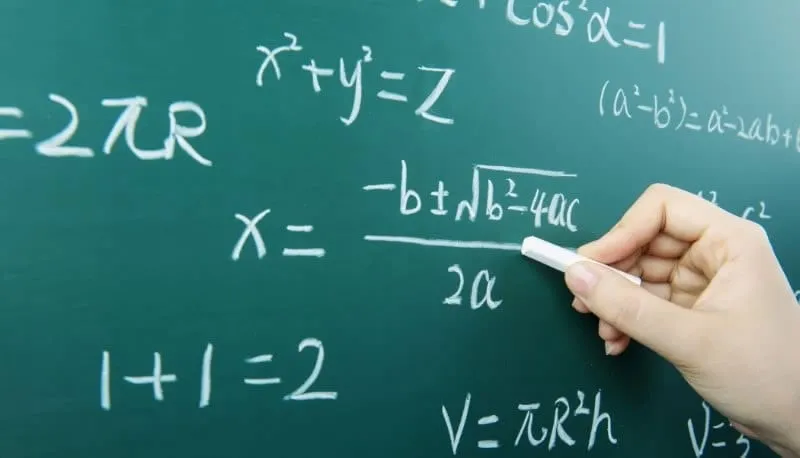- 公開日2024/12/24
- 最終更新日2024/12/24
高校受験における偏差値とは?偏差値60のレベル感や高校生の平均値まで紹介!

目次
高校受験において、「偏差値」は志望校選びや学習計画を立てる際の重要な指標となります。自分の偏差値を正しく把握することで、どの高校を目指すべきか、今の学力レベルがどの位置にあるのかを明確にできます。
本記事では、偏差値の仕組みや平均値、特に「偏差値60」がどのレベルに該当するのかを解説し、受験生が受験勉強を進める上で役立つ情報をお届けします。高校受験を控えた中学生やその保護者の方は、ぜひご参考ください。
高校受験の偏差値とは

高校受験において偏差値は、志望校選びの重要な指標となります。偏差値とは、試験を受けた集団の中で自分がどの程度の位置にいるのかを表す数値のことです。平均点を偏差値50として基準を定め、平均よりも高い点数なら偏差値は50より上に、低い点数なら50より下に位置づけられます。
例えば、ある模試で80点を取った場合でも、その意味は平均点によって大きく変わってきます。もし平均点が60点であれば優秀な成績ですが、平均点が85点だった場合は決して良い結果とは言えません。このように単純な点数だけでは測れない相対的な学力の位置づけを、偏差値は客観的に示してくれます。
また偏差値は、異なるテスト間の成績を比較する際にも役立ちます。問題の難易度が違うテスト同士では単純な点数の比較が難しいものの、偏差値を見ることで自分の立ち位置を正確に把握できます。特に高校受験では、各学校の入試の難易度を示す際に偏差値が用いられることが多く、志望校選びの重要な判断材料となっています。
ただし、偏差値はあくまでも目安の一つです。実際の高校入試では、学力検査の点数だけでなく内申点や面接なども含めた総合的な評価で合否が決まります。偏差値を参考にしつつも、これに過度にとらわれることなく、自分に合った志望校選びを進めることが大切です。
偏差値が決まる仕組みを解説

偏差値は以下の計算式で算出されます。この計算方法によって、異なるテスト間での成績比較が可能になります。
(個人の得点−平均点)÷標準偏差×10+50
模試や定期テストで同じ点数を取得したとしても、平均点の違いによって評価は大きく変わります。例えば、テストAで80点を取り平均点が60点だった場合と、テストBで同じく80点を取ったものの平均点が90点だった場合では、その評価は大きく異なります。テストAでは平均より20点も上回っているのに対し、テストBでは平均より10点も下回っているためです。偏差値を用いることで、このような平均点の異なるテスト間でも客観的な比較が可能になります。
また、テストの点数分布の違いによっても評価は変化します。例えば、英語と数学の2教科で同じ70点を取得し、どちらも平均点が60点だったとしても、得点分布が異なれば偏差値は変わってきます。多くの受験生が高得点を取っている場合と、点数が広く分散している場合では、同じ点数でも評価は異なるのです。
このように偏差値は、平均点との差だけでなく点数分布も考慮した評価方法であり、異なる試験の成績を公平に比較することができます。高校受験においては、この偏差値を活用することで、志望校との実力差を正確に把握することができるのです。
中学生の偏差値の平均や基準とは

中学生の学力を測る偏差値において、50が平均値となります。この数値を基準として、50を上回れば平均以上の成績、下回れば平均以下の成績と判断できます。実際の受験では、この偏差値を参考に志望校選びを行うことが一般的です。
一般的な評価基準では、偏差値70以上は「とても高い」、60以上70未満は「高い」、55以上60未満は「少し高い」とされています。また45以上55未満は「普通」、40以上45未満は「少し低い」、40未満は「低い」と評価されることが多いでしょう。
具体的な数値で見ると、偏差値60の場合は上位15.87%に位置し、1,000人中では158.7位に相当します。偏差値65になると上位6.68%で1,000人中66.8位、さらに偏差値70では上位2.28%となり、1,000人中22.8位という非常に優秀な成績を示します。反対に偏差値40の場合は下から15.87%で1,000人中841.3位、偏差値35では下から6.68%となり1,000人中933.2位に位置することになります。
ただし、偏差値の解釈は所属するコミュニティによっても変化します。市立中学校では「偏差値60は高い」と評価される一方、難関中学校では「偏差値60はそれほど高くない」と判断される場合もあります。環境や母集団によって評価基準が異なることを理解しておく必要があるでしょう。
高校受験における偏差値の役割

高校受験において偏差値は、単なる数値以上の意味を持ちます。志望校との実力差を把握する物差しとしての役割はもちろん、自分の成長度合いを確認する重要な指標としても機能します。正しく活用することで、効果的な受験対策を進めることができます。
志望校と自分の立ち位置を把握する役割
高校選びにおいて、偏差値は重要な判断材料となります。一般的な目安として、自分の偏差値からプラスマイナス3~5の範囲内にある高校を志望校候補とすることが多いでしょう。これは入学後の学習にもスムーズに対応できる範囲とされています。
しかし、偏差値は短期間で大きく変動する可能性を秘めています。例えば中学3年生の7月時点で偏差値56だった生徒が、12月には67まで伸ばして横浜サイエンスフロンティア高校に合格した例や、69から74へと上昇させて横浜翠嵐高校に合格した実績もあります。
受験までの期間が十分にある場合は、現在の偏差値だけにとらわれすぎず、行きたい高校を目指して偏差値を伸ばしていく姿勢が大切です。将来の目標から逆算して計画を立て、一歩一歩着実に実力を伸ばしていきましょう。
前回の自分の立ち位置からどのくらい成長したかを確認する役割
定期的に受験する模試の偏差値は、自分の成長度合いを確認する上で非常に有効な指標となります。前回の模試と比較することで、実力の変化を客観的に把握することができます。
例えば、各教科の偏差値を細かく分析すれば、得意分野と苦手分野が明確になります。また、目標とする偏差値に到達するためには、あと何点必要なのかも具体的に把握できるでしょう。
さらに、不正解だった問題を確認し、どのような対策が必要かを考えることで、より効果的な学習計画を立てることができます。同じミスを繰り返さないよう、しっかりと復習することも大切です。このように偏差値の変化を確認しながら、常に学習計画を見直し、アップデートすることで、着実に実力を伸ばすことができます。
自分の偏差値を把握するには「模試」が有効

高校受験で自分の実力を正確に把握するためには、全国模試や都道府県ごとに特化した大規模な模試を受験することが効果的です。学校の定期テストだけでは、校内での相対的な位置づけしか分からず、実際の受験で競合する地域全体の中での立ち位置を知ることはできません。
首都圏では、進研Vもぎ、新教研W合格もぎ、神奈川全県模試、北辰テストなどの大規模な模試が実施されています。これらの模試を受験することで、より正確な自分の学力レベルを知ることができます。特に志望校が難関校である場合は、その学校に特化した判定模試を実施している塾の模試を受けることもおすすめです。
また、定期的に同じ模試を受け続けることも重要です。これは模試によって受験者層が異なるため、偏差値の数値にも差が出るからです。例えば、難関校を目指す成績優秀な生徒が多く受験する模試では、同じ実力でも偏差値が低く出る傾向があります。
さらに、模試では教科ごとの偏差値も判定されるため、より詳細な学力分析が可能です。目標とする偏差値に到達するために必要な得点も把握でき、不正解だった問題を分析することで、同じミスを繰り返さないための対策も立てやすくなります。
このように模試は、自分の現在の実力を客観的に把握し、効果的な受験対策を進めるための重要なツールとなります。高校受験では地域の受験生全員がライバルとなるため、大規模な模試で自分の立ち位置を確認しながら、計画的に学習を進めていくことが大切です。
【兵庫統一模試】
高校受験を控えてる兵庫県の中学3年生のみなさんには、エディック・創造学園と神戸新聞社が共催する「兵庫統一模試」へのチャレンジをおすすめします。兵庫統一模試では、創造学園が持つ過去50年以上、5万人以上に及ぶ兵庫県全域の入試情報とデータを駆使し、受験生の動向や合格ラインを分析。解説動画の配信などもあり、単なる模試を超えた充実のサポート体制で実力アップが目指せます。詳しくは、「兵庫統一模試」のページをご覧ください
偏差値を把握したあとに高校受験に向けてやるべきこと

模試で自分の偏差値を把握できたら、次は具体的な受験対策に移ります。偏差値は単なる数値ではなく、教科ごとの得意・不得意を把握し、効果的な学習計画を立てるための重要な指標となります。
まずは志望校と自分の偏差値の差を分析し、その差を埋めるための具体的な学習計画を立てていきましょう。
志望校との偏差値ギャップを確認して苦手分野を洗い出す
模試の結果を受け取ったら、個人別成績表で各教科の偏差値を詳しく確認することが大切です。例えば5教科の通算偏差値が60であっても、数学・英語・理科が60に達していないケースがあります。このように科目ごとに偏差値を確認することで、自分の得意分野と不得意分野が明確になります。
偏差値の詳細な分析は、効率的な学習計画を立てる上で重要な役割を果たします。模試では教科ごとの偏差値だけでなく、各設問の正答率や単元別の評価なども示されます。これらの情報を活用することで、どの分野に重点的に取り組むべきかが見えてきます。
また、目標とする偏差値に到達するために必要な得点も把握できるため、より具体的な学習目標を立てることができます。不正解となった問題を確認し、同じミスを繰り返さないための対策を考えることも重要です。
勉強スケジュールを見直して苦手な科目・分野を集中的に強化する
苦手科目や分野が明確になったら、既存の学習計画を見直し、それらの克服に重点を置いた新しいスケジュールを組み立てましょう。この際、得意科目の学習時間を減らして苦手科目に充てるのではなく、全体の学習時間を見直すことが重要です。
模試の結果で明らかになった課題に対しては、集中的な学習時間を確保する必要があります。例えば5教科の総合偏差値は60だが、数学・英語・理科が60に達していない場合、これら3教科を積極的に伸ばすことで、より高い偏差値を目指すことができます。
学習計画の見直しでは、不正解となった問題の分析結果も活用します。同じような問題でミスを繰り返さないよう、しっかりと復習時間を確保することが大切です。また、目標とする偏差値に到達するために必要な得点を意識しながら、計画的に学習を進めていきましょう。
高校受験が不安なら「エディック」におまかせ

エディック創造学園は、兵庫県公立高校入試において圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。特に学区トップ高校では600名を超える合格者を輩出しており、その指導力には定評があります。
生徒一人ひとりの目標に応じて、きめ細かな指導を展開しているのが特徴です。特に近年の入試で重要性を増している長文読解に対応するため、全学年で「速読」を必修化しています。兵庫県の入試問題は他府県と比べて文字数が圧倒的に多いため、読むスピードを上げることで解答時間を確保し、実力を最大限に発揮できる体制を整えています。
また、エディックでは5教科をバランスよく学習できる完全指導体制を確立しています。特に英語では「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく鍛え、理科・社会では知識の活用力を重視した指導を行っています。さらに、定期テスト前にはオンライン自習室を解放し、生徒からの質問にもしっかりと対応します。
習熟度別のクラス編成も特徴の一つです。発展重視のSクラスと基本重視のHクラスに分かれ、同じレベルを目指す生徒同士が切磋琢磨しながら学習を進めることができます。また、中学校別の定期テスト対策も充実しており、内申点対策も万全です。
このように充実した学習環境と実績を持つエディック創造学園で、志望校合格への確かな一歩を踏み出してみませんか。まずは無料体験授業で、実際の授業の雰囲気を体感してください。
自分の偏差値を正しく把握して高校受験を円滑に進めよう!
高校受験において、偏差値は志望校選びの重要な判断材料となります。しかし、偏差値は単なる数値以上の意味を持つものであり、自分の現在の立ち位置を把握し、効果的な受験対策を進めるための指標として活用することが大切です。
兵庫県の公立高校入試では、長文問題への対応力や4技能をバランスよく備えた英語力、さらには理科・社会での知識活用力など、様々な能力が問われます。これらの力を総合的に高めていくためには、現在の実力を正確に把握し、計画的な学習を進める必要があります。
エディック創造学園では、習熟度別のクラス編成と完全5教科指導体制により、生徒一人ひとりの目標に応じたきめ細かな指導を展開しています。特に全学年での速読指導や、中学校別の定期テスト対策など、兵庫県の入試に特化したカリキュラムで確実に実力を伸ばすことができます。
高校受験は決して一朝一夕に対策できるものではありません。早い段階から自分の偏差値を正しく把握し、志望校合格に向けて着実に準備を進めることが重要です。エディック創造学園では、無料体験授業を通じて実際の指導を体感できます。ぜひ一度、授業の雰囲気を体験してみてはいかがでしょうか。